- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
SDGsの時代が始まっている。「働きがいも 経済成長も」「ジェンダー平等を実現しよう」など17の目標からなるSDGsに取り組む企業が増えてきた。消費者たちもSNSを通じて自らの価値観を積極的に発信し、企業はその声を無視できなくなっている。そして企業側も、SNSを通じて自らの社会的価値を発信するようになってきた。こうした流れは今、巨大なうねりとなって世界を変えようとしている。経営トップから「SDGs市民」まで幅広く取材し、現代社会が、そしてビジネスがどこへ向かおうとしているのか、鋭く考察。学生からビジネスパーソンまで必読の書!
目次
まえがき──個人的なことは経済的なこと
「ジャングルジム」型の人生
急速に広がったSDGs、その根底には?
相手の心を知ることから始まる
お金よりも「価値観」の時代
「個人的なこと」がビジネスを動かす
「個人的なことは経済的なこと」
序章 SNS社会が、SDGsの「きれいごと」を広めた
校長先生の「あいさつ」のようなSDGs
SNS社会の「シン炎上」
ツイートに託した願い
背景には「アイデンティティ」
ネット発の企業批判
日本のビジネス、停滞の理由
消費者の「心」をつかんだiPhone
ガソリン車か、「環境に優しい」車か?
株主総会に参加したZ世代
SDGsという共通言語
世界の投資マネーが「ESG投資」に
グレタ・トゥーンベリさんの衝撃
「個人の声」に気づいた経営トップ
第一章 SDGs時代の「市民」たち
SDGs時代を読み解くカギ
「SDGs市民」からの「無限の視線」
「NO YOUTH NO JAPAN」
次々と移り変わる興味・関心
「個人的な思い」が「みんなの思い」へ
「生の言葉」を発信するSDGs市民たち
三菱商事の回答
新たなステークホルダー
企業側から見たSDGs市民
「ウーバー化する社会運動」
可視化される企業の「中の人」
顧客の「個人」領域に入り込む企業
ローソンのプライベートブランド
ツイート分析から見えてきたこと
ローソンの竹増社長、かく語りき
企業はより公共的になっていくのか?
第二章 優等生化する企業
「優等生化」するグローバル企業
「優等生化」に乗り遅れる日本企業
「グレタ・テスト」
「新たな資本主義」を駆動するもの
「ウイグル問題」と日本企業
「見えないリスク」と向き合う
「自分たちのビジネスは社会にとってなぜ必要か?」
サントリーと新時代の日本企業
世界的なアルコール離れの背景
ジェンダーと広告
日本企業が直面するジレンマ
「アイデンティティ」を売るサイボウズ
「個人の言葉」で語るサイボウズ社長
第三章 「正しさ」を求める消費者たち
消費者が有権者化する!?
「冷凍餃子」論争
ある40代女性の話
「モノ言う」消費者たちとSNS
可視化される「みんなの生身の声」
またたく間に形成される「私たち」
「モノ言う消費者」、三つ目の特徴
アイデンティティ経済学
SNS時代の消費者と企業
Z世代と「SDGs消費者」
第四章 衝突するアイデンティティ経済
男性記者の育休体験記事
「つかう側」である消費者の責任とは?
「環境に配慮していますか?」
「民主的なファッション」とSDGs
「働きがいも 経済成長も」
「本社に聞け」
二つの問題
SDGsが分断と衝突をもたらす!?
環境問題ではなく労働問題
ブラック企業では成長できない
波紋を呼んだナイキの動画広告
ナイキの動画はアイデンティティを傷つける?
ビジネスと人権
企業が人権と向き合うとき
中国とのビジネス、どう対峙する?
日本企業の「自画像」をどう描く?
企業のメディア化が招来するもの
ミャンマーのクーデターと日本企業
企業だからこそできること
ビジネスの力
商品・サービスの力
第五章 職場が「安全地帯」になる日
職場で形作られる「アイデンティティ」
部下からの相談
「個人的なこと」が「職場のこと」になる時
「家族」型企業と「チーム」型企業
見えてきた日本の社員像
耐えられないのなら、口を開こう!
社員の「個人的なこと」を上司は知るべし
職場の「心理的安全性」
職場が「安全圏」になる?
職場という「結社」
「オープンな職場」が大事な理由
「自分がダメだから」で終わらせない
「個人的なこと」が発信できる職場を!
最終章 SDGsが「腹落ち」するまでに
「怪しい海外の横文字」
SDGsが「腹落ち」しない理由
「儲け」もいろいろ
ビジネスの本質は「頭の中」に
おカネでは買えない「人の心」
他者とアイデンティティ
「ソフトロー」の力
ムハマド・ユヌスさんの言葉
「見えないもの」の時代へ
仕事だからこそSDGsに取り組める
あとがき──いかにも「アメリカ的な話」
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
kubottar
Risa
Shohei I
あんさん
-

- 電子書籍
- 霜月さんはモブが好き 4 GCN文庫
-

- 電子書籍
- 男と女のゲーム〈恋はポーカーゲームⅡ〉…
-
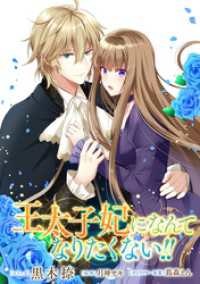
- 電子書籍
- 王太子妃になんてなりたくない!! 連載…
-

- 電子書籍
- 療育に生かす手あそびうた - うたって…





