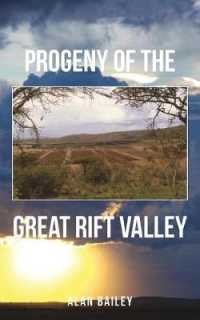内容説明
自己と他者の関係性としての〈ケア〉とは何か。
強さと弱さ、理性と共感、自立する自己と依存する自己……、二項対立ではなく、そのあいだに見出しうるもの。ヴァージニア・ウルフ、ジョン・キーツ、トーマス・マン、オスカー・ワイルド、三島由紀夫、多和田葉子、温又柔、平野啓一郎などの作品をふまえ、〈ケアすること〉の意味を新たな文脈で探る画期的な論考。
本書は、キャロル・ギリガンが初めて提唱し、それを受け継いで、政治学、社会学、倫理学、臨床医学の研究者たちが数十年にわたって擁護してきた「ケアの倫理」について、文学研究者の立場から考察するという試みである。(中略)この倫理は、これまでも人文学、とりわけ文学の領域で論じられてきた自己や主体のイメージ、あるいは自己と他者の関係性をどう捉えるかという問題に結びついている。より具体的には、「ネガティブ・ケイパビリティ」「カイロス的時間」「多孔的自己」といった潜在的にケアを孕む諸概念と深いところで通じている。本書は、これらの概念を結束点としながら、海外文学、日本文学の分析を通して「ケアの倫理」をより多元的なものとして捉え返そうという試みである。(本書「あとがき」より)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
75
他者に配慮し、関係性を結ぶ「ケア」という言葉を文学作品をとおして考察したもの。ここでの「ケアの倫理」で想定されているのは「自己」が互いに“依存し合う関係性”のことである。文学作品として取り上げているのは、ブロンテの『ジェイン・エア』、ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』『オーランドー』、トーマス・マンの『魔の山』、文学論でなくてもいいのにと思いながら、くり返し出てくる「ネガティヴ・ケイパビリティ」「カイロス的時間」「多孔的な自己」の概念的な言葉の世界に浸かった。→2024/12/03
ころこ
46
「100分deパンデミック論」で、著者が『ダロウェ夫人』がスペイン風邪による死者を追悼していると論じていた。第1章で『ジェイン・エア』の読まれ方と対照をなしていると、やはりウルフが論じられている。序文は女性視点の問題が社会学的に、あまりにも率直に書かれている。序章の終わりにある「強さと弱さ、理性と共感、あるいは自立型の自己と依存型の自己のあいだに、いまだ言語化されない不可視のものを見出すことはできないだろうか」という問いに向き合う。ちょうど『おいしいごはんが食べられますように』で女性に向けられた視線を内面2022/10/22
フム
45
育児や介護などのケア労働の多くは女性が担い手であり、社会全体でそれらのケアを引き受けるような政策を取らないかぎりは、今後もこの状況は変わってはいかない。そのためフェミニズムの思想は女性達がケア労働を自ら進んで担うことに批判的だった。そういう批判は社会の公正や正義につながるとわかっていても、女性の一人としてはつらく聞こえることもある。しかし、長い間軽視されてきたケアという活動が、今、問い直されているという。グローバルで多様な価値を認めようとする社会においては、他者を阻害し犠牲にするような絶対的な正義ではなく2021/09/18
ケイトKATE
36
小川公代を知ったのは『100分deパンデミック』に出演した時だった。そこで、ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』をケア小説という形で紹介していたことに驚いた。2020年、新型コロナウイルスの世界規模のパンデミックによってケアの存在が浮かび上がった。しかし、依然として自助や自己責任が優先される今、ウルフをはじめ様々な文学作品から、ケアの意味を読み取っている。ケアは看護や介護するにとどまらず、自分の弱さを認め、他者の苦しみや痛みを知ることもケアを理解する一歩であるという小川公代の考察は新鮮であった。2023/10/24
ケイティ
32
期待以上にケアへの理解が深まると同時に、その概念の幅広さと個別性を思い知る。著者も「ケアへの普遍的な定義は不可能かもしれない」としながらも、人が平等に、互いにケア責任の配分を負いつつ、立場を越えて社会的立場の弱い人々の不安や苦悩に配慮することは可能ではないか、と解く。利他の本でも思ったが、こうしたケアへの探求は即座に実践には至らなくても、折に触れて「これがケアでは」と気づくきっかけとなる。弱者の物語を共有することで、自己と他者の関係性を考えることができ、ケアの倫理はそれを多元的に包括できる。ケア入門に最適2026/02/01
-
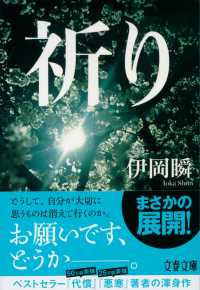
- 和書
- 祈り 文春文庫