内容説明
原子から、生命、機械、コンピュータ、宇宙そのものまで、あらゆる仕組みを説明する「熱力学」。この物理学の最重要分野を切り開き、世界を一変させた科学者たちの知の格闘を熱く物語る!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
27
高校物理でかける時間が少ない分野だからか少し地味な印象のある熱力学だけどその概念の応用は他の分野と比べて抜けている。本書は熱力学を中心とした物理学史でありそれらを築いてきた多くの科学者達の伝記でもあり、物理概念の解説本でもある。蒸気機関から始まり計算機、生物の形成、宇宙のブラックホールまでスケールが広がっていく。原題が「アインシュタインの冷蔵庫」なので熱力学に限定していないことがわかる。数式がほぼなく分かりやすいのだけど高校で物理を履修していないと難しい内容。2024/08/31
まえぞう
21
熱力学は苦手です。理科系であれば、大学の教養課程で必ず学ぶことになりますが、私の躓きの原因だったように思います。この本ではもう少し数式とかがでてくるのかと期待しましたが、熱力学発展の歴史を追う方が中心です。ただ、エントロピーと情報の関係やホーキングとベッケンシュタインが論争を繰り広げたブラックホールとエントロピーの関係の話しは面白かったです。2022/01/25
Bartleby
17
"宇宙を解く"ということだが、私は“時間を解く"鍵が熱力学にあるかもしれないとの期待で本書を読んだ。時間の向きに関して。詳しいむきには当たり前のことかもしれないが、熱力学(エントロピー)→情報科学→生物発生学とつながっていくところに興奮した。早すぎる晩年にアラン・チューリングが発生のデザインを研究していたというがこのあたりをもっと掘り下げたくなった。詳しい方がいたらぜひおすすめの本を教えてください。「拡散によって構造が作られる」という一見直感に反する真理には興奮を超えて歓びさえおぼえた。2022/10/24
toshi
10
熱力学の発達の歴史をたどりながら分かり易く解説した本。 カルノー、ジュール、マックスウェル、ボルツマン、プランク・・・・といった大学の講義で、法則・方程式・定数などで登場した人物の背景と歴史的な仕事を紹介していて、ただ暗記するだけの式や定数が何となく身近になった。熱力学の歴史の中にこんなエピソードが有ったのか・・・という話ばかりで面白く読めた。終盤の情報量を熱力学と結びつける話と、宇宙全体をブラックホールに例える話ははじめてで目から鱗。2021/07/31
ブック
7
熱力学の発展の歴史が、それぞれの科学者の人間ストーリーの連なりとして表現されている。あとがきにあるように、人類が熱力学について正しく理解することが、気候変動対策のカギになるという狙いには強く共感する。熱力学は今や熱の力学だけではなく、社会学などにも応用されていて、ある種の「真理」を表しているように感じる。特に第二法則のエントロピー増大則を知っているかどうかが、人類の未来の持続可能性に大きく影響する。それにしても原題「アインシュタインの冷蔵庫 温かさと冷たさのちがいがいかに宇宙を説明するか」は洒落ている。2023/03/18
-

- 電子書籍
- 子連れママのデキちゃった恋【タテヨミ】…
-
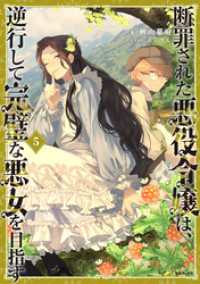
- 電子書籍
- 断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪…
-
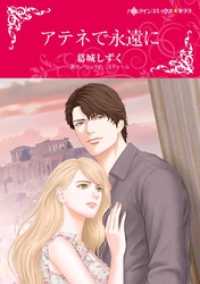
- 電子書籍
- アテネで永遠に【分冊】 9巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- ず・ぼん15-7 - 今、アメリカの図…





