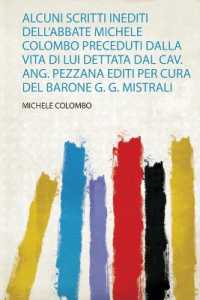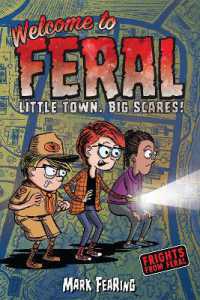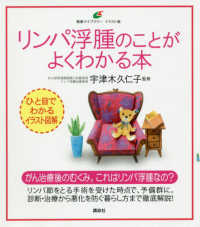内容説明
ストーンヘンジは夏至の日の出を示し、ピラミッドは正確に真北を向いて建造されている。古代人は星空から精密な方角や暦を導き出している。どの星を頼りに計測したのか、当時の星空から読み解く!
目次
はじめに
天文学が考古学の研究を進める
古天文学の三つの分類
第一章 巨石文化は何を示しているのか?
1 ストーンヘンジは天文学の事象を予測していた?
古天文学と巨石文化
巨大遺跡の四つの分類
ストーンヘンジについて
2 遺跡を科学的に考察するための天文知識
位置天文学とは何か
天球と二つの座標
地平座標
赤道座標
日周運動
南中と天体の出没方位
太陽の動き(黄道)と季節
季節や緯度で日没のようすが変わる
月の話 白道とは
出没方位図とスタンドスティル
月の出入りと遺跡の関係
地球の歳差運動とは
3 古天文学の視点で巨石遺跡を見る
ストーンヘンジの分析
ストーンヘンジはアナログ・コンピュータだった?
メジャー・スタンドスティルと二つの巨石遺跡
日本の巨石遺跡
巨石文化と天体観測
第二章 太陽信仰とピラミッド
1 ピラミッドはどこを向いているか
ミューオンで進んだピラミッドの研究
階段ピラミッド
屈折ピラミッド
真正ピラミッド
三大ピラミッド
ピラミッドの方位は歳差でずれている
天の北極を定める二つの説
建造年で微妙にずれるピラミッドの向き
北極星は何時に真北になるのか
太陽を使って「南」を計測する
エジプトの太陽信仰とは
2 暦はどうして生まれたのか
暦はなぜ必要か
春分や秋分でも昼の方が長い
曜日の起源は太陽系の惑星
「月」は月齢に因んでつくられた
3 エジプトの暦と天体の関係
月の満ち欠けをもとにした太陰暦
季節に合わせた太陰太陽暦
なぜエジプトで太陽暦が生まれたのか
360日に5日が加わった神話
ユリウス暦とグレゴリオ暦
3000年で1日ずれる
第三章 暦とマヤ文明
1 ピラミッドが暦をあらわしている
マヤ文明とは
マヤ文明の歴史 先古典期
マヤ文明の歴史 古典期
チチェン・イッツァ
暦のピラミッド
春分にうねる蛇
チチェン・イッツァの天文台と球技場
マヤ文明の衰退
2 天体観測をしていた!
マヤ文明の特徴 宇宙観と数字
太陽暦と優秀な天体観測技術
太陽暦と儀礼暦のカレンダーラウンド
金星の光でも影ができる
地球と金星の会合周期
太陽暦と儀礼暦と金星
長期暦
第四章 広大な海とポリネシア
1 海を渡るために発展したポリネシアの天文学
オセアニアの三つの地域
メラネシアとミクロネシア
ポリネシア
天測暦
灯台守はいなくなった
太陽を用いた方位の確認
季節ごとに目印となる四つのグループ
冬の目印の星と星座
春の目印の星と星座
夏の目印の星と星座
秋の目印の星と星座
航海のための星
2 星にまつわる物語
星の民話
ホクレア号
ポリネシアを西欧に知らしめた人物と天文現象
西欧にポリネシアを紹介したキャプテン・クック
金星の太陽面通過の観測
ビーナス・ポイントで見たグリーンフラッシュ
日本にも来た金星の太陽面通過の観測隊
第五章 世界最古の天文図、キトラ古墳
1 日本の古天文学はどうなっているか
日本の古天文学の研究対象「キトラ古墳」
キトラ古墳の調査
天文図の重要な五つの要素
古代中国星座の基本は28宿と4神
中国と西洋の星座のちがい
正距方位図法で描かれた星座
星や星座が沈まない内規
見ることのできない外規
2 キトラ古墳に描かれた星図はいつのもの?
キトラ古墳の古天文学の二つの研究
描き込まれた赤道、黄道、内規、外規
赤道と内規の半径の比で緯度がわかる
星宿図の原図の観測年代は?
28宿の五つの星から観測年代を推測
六つの星から内規の緯度を推定して作成地域も特定
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
へくとぱすかる
みつ
buchi
kurupira
-

- 電子書籍
- 茶葉少女~蟲に食べられそうになったら、…