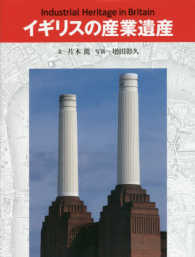- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
大正時代の日本は、さまざまな外来の文物を貪欲に受け入れ、豊かな社会の到来もあって新たな思想や価値観、生活スタイルや芸術文化を生み出した。労働運動がさかんになり、デモクラシーへの要求が強まるとともにナショナリズムも勃興する。教養主義が成立し、女性の地位が変わり始めるなか、大衆社会化によって多様な消費文化が生まれていった。百花繚乱ともいえるこの時代の文化を、二五人の研究者による最新成果を結集して、イデオロギーにとらわれることなく、正確に描き出す。
目次
はじめに……筒井清忠
大衆の登場と修養主義の盛行
修養主義からの教養主義の分離
日本のエリート文化はなぜ脆弱だったか
巨大な大衆化・同調圧力の国へ
第1講 吉野作造と民本主義……今野 元
西洋(西欧)派日本ナショナリズムへの道
東京帝国大学法科大学での擡頭
西洋体験とその影響
大正デモクラシーの論客
普通選挙運動・社会主義政党支援・国際協調
大正デモクラシーの終焉と吉野作造の死
敗戦後の吉野作造
第2講 経済メディアと経済論壇の発達……牧野邦昭
経済雑誌の登場
『東洋経済新報』と『ダイヤモンド』
『中外商業新報』と『エコノミスト』
学術経済雑誌と個人雑誌
総合雑誌における経済論争
経済メディア・経済論壇の発達がもたらしたもの
第3講 上杉愼吉と国家主義……今野 元
日本国家の主体性を求めて
東京帝国大学法科大学での擡頭
西洋体験とその影響
天皇機関説論争
民本主義論争
国家総動員の構想
国家総動員体制の成立と日米戦争
第4講 大正教養主義――その成立と展開……筒井清忠
修養主義の登場
ケーベルの教養主義とエリート文化
旧制高校の変化と教養主義受容
マルクス主義と教養主義
教養主義の波
第5講 西田幾多郎と京都学派……藤田正勝
教養と文化
西田幾多郎のT・H・グリーン研究
教養主義
人格主義
文化主義
ドイツの文化哲学の影響
カントおよび新カント学派の研究
第6講 「漱石神話」の形成……大山英樹
「三四郎」から「三太郎」へ継承されたもの
漱石の死から始まる「則天去私」神話
小宮豊隆による「聖人化された漱石像」の構築
「岩波文化」というレッテル
江藤淳による新しい漱石像の提示
「漱石神話」はかたちを変えて受け継がれる
第7講 「男性性」のゆらぎ――近松秋江、久米正雄……小谷野 敦
「恋に狂う男」の誕生
近松秋江の描いた「情けない男」
面白いが読まれなかった秋江
振られた男への同情で売れた久米正雄
中産階級の女性人気を得た「童貞」的青年像
新たな青年像を生んだ大正という時代
第8講 宮沢賢治――生成し、変容しつづける人……山折哲雄
雨ニモマケズ斎藤宗次郎
「デクノボー」願望
「ヒデリ」と「ヒドリ」
方言と高村光太郎
宗教と文学
賢治像の行方
第9講 北原白秋と詩人たち……川本三郎
公の明治から私の大正へ
荷風の葛藤
白秋の父との相克
文学が輝きを持ち始めた時代
孤高の芸術の美しさ
第10講 鈴木三重吉・『赤い鳥』と童心主義……河原和枝
「お伽噺」から「童話」へ
『赤い鳥』の童話
『赤い鳥』と『少年 楽部』
「弱さ」と正義
「無垢」=「童心」の理想
「童心」の時代
第11講 童謡運動――西條八十・野口雨情・北原白秋……筒井清忠
西條八十と野口雨情
「かなりや」の衝撃
白秋と雨情・八十の対立
童謡観の対立
ポピュラリティーと芸術
童謡界の惑星・金子みすゞ
金子みすゞへの八十の影響
大正期童謡の意義
第12講 新民謡運動――ローカリズムの再生……筒井清忠
「民謡」概念の成立
地方民謡の東京進出
西條八十による民謡の発見
全国化した地方民謡の代表曲
野口雨情と新民謡運動
地方・民衆の逆襲
ローカリズム確立競争
第13講 竹久夢二と宵待草……石川桂子
誕生から上京
独学、雑誌投稿からデビューへ
「夢二式美人」誕生
「港屋絵草紙店」開店と大正期の画業
遅すぎた外遊
「宵待草」作詩と楽譜出版
「宵待草」と大正文化
「大正ロマン」の発祥
「大正ロマン」と夢二
第14講 高等女学校の発展と「職業婦人」の進出……田中智子
『はいからさんが通る』の世界
高等女学校制度の成立
高等女学校とならない女学校
高等女学校の拡大
揺らぐ良妻賢母教育
「職業婦人」の登場
「職業婦人」とは誰なのか
『はいからさんが通る』の射程
第15講 女子学生服の転換――機能性への志向と洋装の定着……難波知子
着物の弊害と改良服の試み――女子学生服としての袴の成立と普及
第一次世界大戦の影響――欧米女性服の変化と日本における受容
統一の洋装と自由な洋装――服装自由に込められた教育的意図
女子学生服の画一化――流行によるセーラー服への集中
第16講 「少女」文化の成立……竹田志保
「少女」研究の現在
少女雑誌の登場まで
少女雑誌の興隆
読者欄と投稿者たち
吉屋信子『花物語』が描いたもの
少女雑誌のその後
第17講 大衆文学の成立――通俗小説の動向を中心として……藤井淑禎
通俗小説と家庭小説
新聞小説と新聞拡販競争
大戦景気と雑誌ブーム
芥川龍之介と長田幹彦
純文学と通俗小説
『講談 楽部』と『新青年』
代表的な通俗小説
第18講 時代小説・時代劇映画の勃興……牧野 悠
娯楽読物の革新期
『立川文庫』と忍術ブーム
『講談 楽部』の〈新講談〉
〈捕物帳〉と〈伝奇小説〉
出没する鞍馬天狗と直木三十三
最盛期の幕開け
映画界への波及効果
第19講 岡本一平と大正期の漫画……宮本大人
漫画史における大正期
明治期における「漫画」の形成
楽天の政治性、一平の脱政治性
漫画漫文形式の確立
漫画家の地位向上
漫画で「人間」を描くこと
第20講 ラジオ時代の国民化メディア――『キング』と円本……佐藤卓己
ラジオ放送の開始
「全国メディア」の成立
「声の出版資本主義」と大日本雄弁会講談社
『大正大震災大火災』の成功から
書籍の雑誌的販売――改造社『現代日本文学全集』の成功
円本ブームから派生した「国民的教養」メディア
第21講 大衆社会とモダン文化――商都・大阪のケース……橋爪節也
〝大大阪〟の誕生
大大阪モダニズムと阪神間モダニズム
「大大阪君似顔の図」
もうひとつのベクトル――浪花情緒
第22講 大衆歌謡の展開……倉田喜弘
女性の社会進出
カチューシャの唄
船頭小唄
籠の鳥
レコードの電気吹込
第23講 発展する活動写真・映画の世界……岩本憲児
活動写真時代
新派映画と女形
純映画劇運動と女優の誕生
映画劇への模索
欧米映画の影響
民衆娯楽の先頭に立つ
第24講 百貨店と消費文化の展開……神野由紀
日本における初期百貨店とその転換
ターミナル・デパートの出現と郊外住宅地の発展
銀座の震災復興と盛り場の再編
家族と消費生活
趣味の創出と流行操作
おわりに――消費の欲望喚起装置としての百貨店
第25講 阪急電鉄と小林一三――都市型第三次産業の成立……老川慶喜
大衆消費社会の誕生
箕面有馬電気鉄道の創業
北浜銀行事件と神戸線の開業
住宅地・家屋の販売と電灯電力の供給
箕面動物園と宝塚新温泉
阪急百貨店の開業
芋蔓式経営と大衆本位の事業
第26講 宝塚と小林一三……伊井春樹
箕面有馬電気軌道鉄道の頓挫からの発足
箕面、宝塚での集客策
宝塚少女歌劇団の発足
松竹と宝塚少女歌劇との競合
宝塚少女歌劇団の東京進出
第27講 カフェーの展開と女給の成立……斎藤 光
当初のカフェー
一九一一(明治四四)年の銀座
カフェーの内実――ライオンの事例(大正四年)
『中央公論』における批評(大正七年)
「女給」の誕生と普及(大正一一年)
関東大震災のインパクト(大正一二年・一五年)
おわりに――大阪での新機軸
編・執筆者紹介
凡例