内容説明
日本の保護者の教育費負担は非常に重いが、公教育費負担を増やすべきという社会的な声はあまり大きくない。しかし私的負担の重さは、少子化の促進や教育機会の不平等の拡大につながる。社会保障や福祉と教育の機能を考察しつつ、財政難という条件にある日本において、公教育費を増やすにはどうしたらいいのか、そのヒントを探る。
目次
序章 少なすぎる公教育費
1 閉塞した教育費をめぐる問題
2 公教育費は増やせるのか
第I部 教育費をめぐる人々の意識と政策の現状
第一章 教育の社会的役割再考
1 「教育」の浸透する社会
2 近代化と教育─社会学的に学校教育を振り返る
3 教育の社会的機能再考
第二章 国家・政府と教育
1 政府にとっての教育
2 近代国家の成立と教育システムの整備
3 国家機構の整備と世界への普及
第三章 教育と社会保障・福祉との関係性
1 社会政策としての教育
2 日本の教育政策と背景の福祉制度
3 グローバル化する世界と社会政策
4 国際比較から見る教育制度と社会保障・福祉制度との関連
第四章 国際比較から見た日本の教育・社会政策への意識構造
1 福祉政策・社会保障に対する態度
2 社会政策の規定要因
3 国際比較分析
第II部 教育の公的負担が増加しなかったのはなぜか
第五章 日本の財政と教育
1 政府の赤字財政の原因
2 財政と予算
3 負担と利益のバランス
第六章 教育費高騰の戦後史
1 戦後民主主義教育体制の発足と教育費の負担
2 高度成長期から安定成長期にかけての教育費
3 恒常化する重い教育費負担
第七章 教育費をめぐる争点
1 自己責任と化する教育費負担
2 選挙の公約・マニフェスト
3 民主党政権の掲げた教育政策への賛否
第八章 政策の実現と政党に対するスタンス
1 「官」に対する厳しい眼差し
2 間接民主制における民意の反映
3 政党支持と政策への態度の関係
終章 教育を公的に支える責任
1 「失敗」に対する寛容
2 教育と公共性・教育の公的負担に向けて
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
アナクマ
まるさ
りょうみや
安藤 未空
-
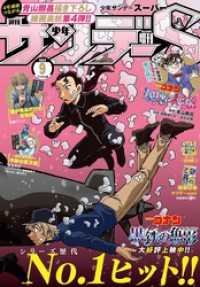
- 電子書籍
- 少年サンデーS(スーパー) 2023年…
-
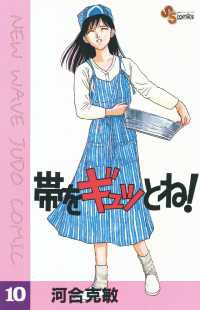
- 電子書籍
- 帯をギュッとね!(10) 少年サンデー…







