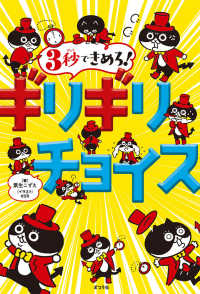内容説明
なぜ教育には「~しなければならない」が多いのか? どうすれば「みずから学ぶ」環境はつくれるのか? 教え方ではなく、子どもの学びの深め方からいま必要な教育の本質を考える。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
25
地球環境の破壊が進み、共生が求められるこれからの社会に必要な学びについて論じている。物事を分類ないし分節化する近代の知識に対し、自然と身体が融合するような感性の所作としての知識がこれからは大切だという。いわゆるホリスティック教育である。 18万人が不登校状態にある学校教育は、系統的知識の伝授にこだわり、子どもの主体的な問いに応えられるようなプログラムを提供できない。グローバルな規模で環境共生が求められる時代にあっては、詰め込み型の知識を反復する力ではなく、主体的に社会に関わる力が必要だという。良書なり。2021/12/25
はる坊
19
教える側の視点に立つのではなく、学ぶ側の視点に立つ。 これからは学びが重要と説く。 すごく大切なことがたくさん書かれていたけど、きちんと整理出来てないので、再読予定。2021/08/22
nagata
11
教えるもの、育つものが分断されたまま、一方的な教授が当然だった教育を根っこから捉え直し、教えから学びへの転換という根本的な問いかけは響くものがある。「はじめに」の呼びかけから核心にスバっと切り込んでいく語り口は最後まで色褪せなかった。2026/01/07
コジターレ
9
読者に柔らかく問いかけ続けるような本だった。だから読者としてそこに答えざるを得ず、時折立ち止まって思考するので、読み終えるのに随分時間がかかってしまった。この国の教育に強い危機感を覚えながら、力みなく、押し付けることなく、断定的な言い方をすることなく、「問いかける」ことができる著者の姿こそ、教師に求められる姿なのだろう。そして、著者の深い教養と人間に対する温かい眼差しも印象的だ。本の内容もさることながら著者の生き方が、本書のサブタイトルでもある「教育にとって一番大切なこと」を伝えている。2025/09/23
shimashimaon
9
Voicyで「のもきょう」さんの配信を聴いて読むことにしました。「不登校」を「問題」にすること自体ナンセンスだと理解しました。「学び」は主体性や積極性が重視されるだけでなく、著者は受け身passiveであることから学びは始まると言います。それは消極的な態度ではなく、passion(感情の他にイエスの受難という意味がある)と語源が同じであることから、困難から逃げるのでなく受け止めるというポジティブな態度だと説明します。「語義」の暗記ではなく「意味」の体験を。私もその体験に一役貢献できないかなと考えています。2023/12/09


![深川慕情 取次屋栄三[13]<新装版> 祥伝社文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2228290.jpg)