内容説明
2020年10月に60歳の還暦を迎える齋藤孝。
それまでに培ってきた「生き方の技」の数々を、50歳代から60歳代の読者に向けてカスタマイズし、知恵のエッセンスが惜しげもなくギュッと凝縮された「集大成本」。
「生き方の技の集大成」が具現化されたのが「円熟した大人」です。
「円熟した大人」が持っている(持つべき)資質は次の10の要素です。
○過去や現在にこだわらず軽々と変化できる「シフトチェンジ力」
○腰と肚がすわっている自然体と「身体感覚力」
○いつも笑顔で「場」を暖める「上機嫌力」
○雑談の重要性を分かっている「大人のコミュニケーション力」
○「塩梅」「相場」「中庸」を弁えた「添う力」と「ずらす力」
○身体性を生かした「読書力」
○日常感覚と日本の伝統に基づいた「美意識力」
○意志に裏付けられた「孤独力」
○あっけらかんとした「ingの死生観」
目次
■はじめに 「円熟した大人」の作り方
二つの「新しい生き方」
生きているだけで丸もうけ
円熟と成熟の違い
死ぬまで学ぶ
■第1章 60代はシフトチェンジする時期
なぜシフトチェンジが必要か
「コントロールできないもの」を見極める
経済的人間から文化的人間へシフトチェンジ
「ミニ創造者」と「ミニ享受者」
文化の享受は「貢献」を生む
ミニ創造者+ミニ享受者=ミニ創造享受者
「贈り物」社会へシフトチェンジ
「いいパス」を出す大人になる
「競争」から「遊び」へシフトチェンジ
遊びの4つの要素
「他者評価」から「自己評価」へシフトチェンジ
自己評価には、他者が入り込んでいる
「もう一人の自分」を基準軸にする
「頭脳」から「身体」へシフトチェンジ
レスポンスする身体
円熟した大人は「中庸」へシフトチェンジ
矛盾を生きる力
■第2章 「身体感覚力」を取り戻す
失われていく身体文化
「腰肚文化」
腰と肚は心身の中心感覚と軸感覚を作る
「自然体」という身体技術
自然体の作り方
天と地を貫く「軸」を作る
「型がなければ、形なし」
型は、現実世界の「座標軸」
型の抵抗が人間の成長を促す
個性は型を通して形成される
「技」は「型」の反復で得られる
「技」とは身体の繊細な動かし方
達人たちの技
「間、髪を容れず」と「石火の機」
心をどこに置くか
未だ木鶏たりえず
自然体は、他者との「距離感覚」に優れている
場とは
息の文化
息とは生命そのもの
齋藤式呼吸法
人は息でコミュニケーションする
相手の息づかいに寄り添い、寄り添われる
間のいい人、間の悪い人
息は「コツ」
気には「内の気」「外の気」「間の気」がある
「気がきく人」は生き残る人
幸田露伴の「気」
些事徹底
張る気
声は、身体が響き合う音楽
声は人格
素読・音読の大切さ
音読は人生をつなぎ直す
■第3章 上機嫌力
不機嫌なシニアは嫌われる
上機嫌を「技」として身につける
上機嫌は円熟した大人の義務である
アランの『幸福論』
「ピン」を探せ!
上機嫌力は、自然体を作ることから始める
「ふっきり上手」になる
「断言力」でふっきる
「想像力」でふっきる
「笑い飛ばす力」でふっきる
「エスプリ」と「ユーモア」
「自分を笑い飛ばす」ことは自己客観視
「自画自賛」上手になる
自画自賛は、他者とつながる手段
「自己客観視」上手になる
上機嫌を招く簡単テクニック
■第4章 大人のコミュニケーション術
60歳からの交際術
雑談名人を目指す
コミュニケーションの可否は「場」が決める
「意味」の意味、「感情」の意味
「意味」と「感情」の座標軸
円熟した大人同士の雑談「Aゾーン」
「文脈」は「流れ」と「つながり」
人は話すだけで、4本の文脈でつながる
もう一つ大切な4番目の文脈
コミュニケーションの「二重性」に気をつける
■第5章 「添う力」
まず「添う」こと
次は「ずらす」
「添いつつ、ずらす」は東洋的な考え方
らせん状に上昇していく会話
至るところで見つかる「添いつつ、ずらす」
「添う」力
聞く力のメリット
聞く身体
相手の身体に同調する
時間差おうむ返し
聞く難しさ
聞く力を邪魔する「自己顕示欲」と「権力欲」
自分を空っぽにする
「いるだけでいいんだ」と伝える
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ショウジ
Masa
-

- 電子書籍
- どうしようもないアイツ10 オパールC…
-

- 電子書籍
- 今度こそ、この結婚を回避します~愛のな…
-
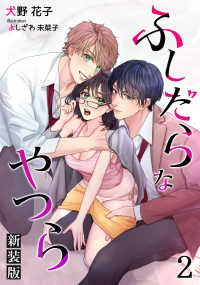
- 電子書籍
- ふしだらなやつら(新装版)【分冊版】2…
-
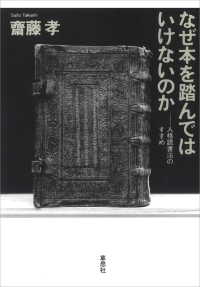
- 電子書籍
- なぜ本を踏んではいけないのか:人格読書…
-
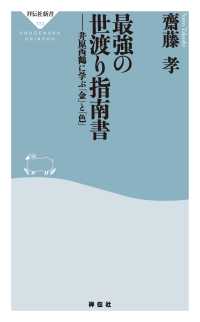
- 電子書籍
- 最強の世渡り指南書――井原西鶴に学ぶ「…




