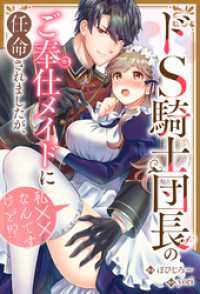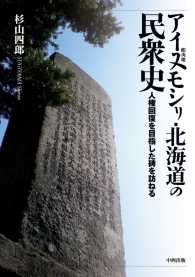内容説明
森の中で巨樹を伐る。轟音を立てて倒れ、生命が絶たれたように見える。だがしばらくすると切り株から小さな芽が生まれてくる。死んだと思った木は生きていたのだろうか? 植物の「いのち」は、わたしたち動物とはずいぶん違って見える。動かず、しゃべらず、食べない。一方で、栄養を自分で作る、体の一部が失われても復活するなど、動物には真似できない能力も持つ。ユニークな「いのち」の形と仕組みをやさしく解説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
108
私たち人類の遠い同族の植物。身近に居ながらその生態はホモサピエンスとは当然違う。気になったトピックを3箇所。①樹木の葉は冬の寒さの訪れが近づくと「自分はまもなく役に立たなくなる」とし、枯れ落ちる支度をする。②数十年の樹齢を重ねたイチョウの木は分厚い樹皮で覆われているが春に幹の低い所から若い芽が出る「分化全能性」がある。③日本では樹齢3000年以上と言われる縄文杉があるが、アメリカにはカロリナポプラと言う樹齢約8万年の「樹木の森」がある。但し、樹木は200年程度で地下に根で4万本と繋がり重さは6000トン。2022/05/02
クリママ
51
植物が好きと言いながらも、何も知らなかったことが分かった。縄文杉のように数千年も生き続けている樹木。花を咲かすということは、植物にとってどういうことなのか。根から水を、葉から光を吸収するしくみ、命をつなぐしくみ、等々、わかりやすく書かれている。この本が最新刊のようだが、植物についての多くの著作があり、もっと読みたいと思う。2022/06/21
あるにこ
13
知っているようで知らない身近な植物。そんな植物の生き方について書かれている。得意な季節で勝負し、種となって休眠するもの(2000年前の種を植えたら生えてきて事例もある)や、冬の寒さにも耐えられるよう糖分を増やし凍らないように対策した常緑樹など生き方は多岐にわたる。また、寿命について長いものは8万年!ただ、8万年は根の年齢で、実際に見える樹木は200歳ほどとのこと(それでも十分スゴい)。動物とは全く異なる生き方をしているのだなとしみじみ。植物に興味を持てる内容でした。2021/06/10
paluko
10
2021年発行ということで、植物がいかに「密」を避ける工夫をしているかとか、コロナ対策になぞらえた例えが随所に登場。身近な園芸植物や野菜のことでも実は基本的なことで知らなかったことが沢山。ジャガイモで食用にするのは植物体の「茎」の部分なのに対しサツマイモは「根」の部分だとか、キンモクセイやジンチョウゲなど日本には「雄株」しか入っていないために種を取ることができない植物があるとか、ナシの品種「二十世紀」は1888年に「現在の千葉県松戸市の民家のゴミため場の中で、芽生えて」(213頁)いたものが起源だとか…。2023/12/06
紙狸
10
2021年5月刊行。新型コロナ流行の中で接した「はじめに」が心にしみる。感染拡大を防ぐための生活様式(外出の自粛、言葉を発しない、密を避ける)について、植物の生き方との類似性を説く。タイトルから分子レベル(DNAなど)の研究成果を盛り込んだ本かと想像したが、違っていた。細かくなっても細胞まで。印象としては、中学の理科で習った生物の知識を前提に、動物とは異なる植物らしさを説明した本。樹齢はずいぶん長くなり得るのだな.三春町の「三春滝桜」は1000年を超えているのか。2021/05/19