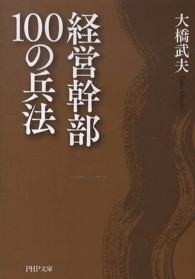内容説明
社会学や文化人類学における新たな研究方法として、医療、看護、臨床心理、社会福祉等の臨床領域における新たな実践方法として、さらには紛争調停や組織経営の新たな手法として分野の壁を超えて注目されるナラティヴ・アプローチ。本書は各分野を代表する研究者の最新成果を集約し、その独自の意義と可能性を明らかにする。
目次
はじめに[野口裕二]
序 章 ナラティヴ・アプローチの展開[野口裕二]
1 概念と前提
2 ナラティヴの多様性
3 ナラティヴ・アプローチの多様性
4 対象の水準と検討すべき課題
第一章 エスノグラフィーとナラティヴ[小田博志]
1 エスノグラフィーとナラティヴ
2 他者との関係を語る
第二章 オルタナティヴとしてのリフレクティング・プロセス ナラティヴ・アプローチへのシステム論的処方箋[矢原隆行]
1 ナラティヴ・アプローチの観察
2 ナラティヴ・アプローチの隘路
3 リフレクティング・プロセスの概要
4 オルタナティヴとしてのリフレクティング・プロセス
5 おわりに
第三章 医療におけるナラティヴ・アプローチ[小森康永]
1 新しい慢性疾患治療援助としての外在化心理教育
2 新しい医師患者関係構築としての共同研究
3 新しいターミナルケア/遺族ケアとしてのリ・メンバリング実践
4 新しい医療メディエーション(調停)としてのナラティヴ
5 おわりに
第四章 看護学とナラティヴ[大久保功子]
1 看護学の知の変遷と質的研究
2 ナラティヴ・ナレッジの発掘
3 共に現実を創るナラティヴ
4 看護学におけるナラティヴ・アプローチ
第五章 私の家族療法にナラティヴ・セラピーが与えた影響 ナラティヴを取り入れた新たな家族療法の臨床実践[吉川悟]
1 家族療法からナラティヴ
2 私にとってのナラティヴの実践初期
3 臨床の考えにナラティヴを取り込む
4 再び家族療法にナラティヴを取り込む
5 治療者の違いは事例表記にあらわれるか
6 私的考察
第六章 社会福祉領域におけるナラティヴ論[木原活信]
1 はじめに
2 社会福祉領域におけるナラティヴ関連文献のレビュー
3 ナラティヴ論とその系譜
4 伝統的ソーシャルワークとの差異
5 浦河べてるの家の「幻聴」から「幻聴さん」の実践
6 むすびにかえて――ナラティヴ運動の時
第七章 生命倫理とナラティヴ・アプローチ[宮坂道夫]
1 英語圏でのナラティヴ・アプローチ
2 臨床事例へのナラティヴ・アプローチ
3 架空の事例研究
第八章 紛争をめぐるナラティヴと権力性 司法へのナラティヴ・アプローチ[和田仁孝]
1 ナラティヴと権力性
2 司法のナラティヴ構造
3 医療紛争におけるナラティヴの交錯と権力
4 司法の相対化――ナラティヴ・アプローチの実践性
第九章 組織経営におけるナラティヴ・アプローチ[加藤雅則]
1 はじめに
2 組織論における語り
3 組織経営におけるナラティヴ・アプローチ――事例紹介
4 事例の考察
5 おわりに
終 章 ナラティヴ・アプローチの展望[野口裕二]
1 ドミナント・ストーリーをめぐって
2 基本アイディアとしての「いまだ語られていない物語」
3 ナラティヴの多元性と重層性
4 和解の物語、希望の物語
5 おわりに――実証性と事例性をめぐって
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぷほは
かえるくん
NaCl
コジターレ
Arick
-
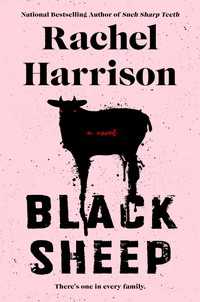
- 洋書電子書籍
- Black Sheep