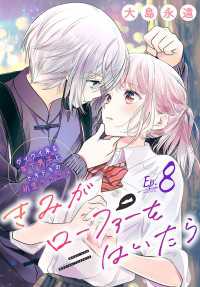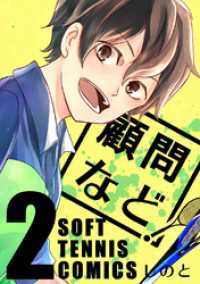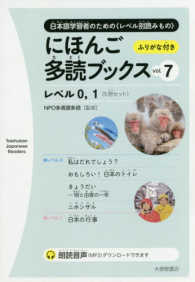- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
1980年代初頭、多くの人が「漫才ブーム」に熱狂した。その影響のもと、私たちは何かあればボケようとし、それにツッコミを入れるようになった。笑いが、重要なコミュニケーション・ツールとなったのである。そこにおいてシンボル的な存在となったのが、タモリ、たけし、さんまの「お笑いビッグ3」だった。先鋭的な笑いを追求して90年代に台頭したダウンタウン、M―1グランプリから生まれた新潮流、そして2010年代に入って頭角を現した「お笑い第7世代」……。今なお中心的存在であり続ける「ビッグ3」を軸に、日本社会の「笑い」の変容と現在地を鋭く描き出す!
目次
序章 笑いは世界の中心に──なぜいま、タモリ、たけし、さんまなのか?
2018年に起きた〝事件〟
「お笑いビッグ3」誕生の瞬間
可視化された「笑う社会」
笑いは世界の中心に
漫才ブームと「ビッグ3」それぞれの関係
「笑う社会」に変化の兆し
本書の流れ
第1章 「お笑いビッグ3」、それぞれの軌跡──80年代まで
1 変わらぬ趣味人・タモリ
ジャズとの出会い
ルール嫌いの森田少年
一度目の上京
二度目の上京
遅れてきた大学生
「恐怖の密室芸人」
変わらぬ趣味人
2 理想の悪ガキ・ビートたけし
貧乏と悪ガキどもの世界
母の教育
「みな っ八」にみえた新宿時代
即興芸としてのコント
「ひとり団塊世代」たけし
コントから漫才へ
理想の悪ガキ
3 笑いの教育者・明石家さんま
学校の人気者
落語家からタレントへ
吉本新喜劇とテレビ、その密接な関係
最初のテレビっ子芸人
転機となった『ヤングおー!おー!』
『オレたちひょうきん族』で全国区の存在に
「笑いの教育者」としてのさんま
第2章 「お笑いビッグ3」とダウンタウンの台頭
1 ダウンタウンの東京進出と「お笑い第3世代」
芸人世代論の始まり
NSC、誕生
尼崎というルーツ
ダウンタウンの苦闘
「2丁目現象」で若者のアイドルへ
「お笑い第3世代」と『夢で逢えたら』
テレビを遊び場にしたとんねるず
お笑い第3世代・ダウンタウンの試練
2 ダウンタウンが起こした〝革命〟
東京での初冠番組『ガキ使』
『ガキ使』フリートークという革新
『ダウンタウンのごっつええ感じ』スタート
突破口になった「おかんとマーくん」
「トカゲのおっさん」という到達点
視聴者が芸人に試される関係に
松本人志の使命感と『ごっつ』の終了
3 「お笑いビッグ3」とダウンタウン
「しょーがねーなー」という立ち位置
北野武と松本人志の類似点
お笑いから離れ始めたたけし
MCの時代をリードしたさんま
さんま vs. 素人
タモリとオチのない笑い
趣味人・タモリへの道
芸人世代論はなぜ1990年代に定着したのか?
第3章 『M‐1グランプリ』と「お笑いビッグ3」
1 ダウンタウンが「スタンダード」に
「前衛」から「スタンダード」へ
『24時間テレビ』のダウンタウン
ダウンタウンを中心にした「笑いの共有関係」
島田紳助という理解者
2 『M‐1グランプリ』という〝実験場〟
『M‐1グランプリ』誕生
松本人志、M‐1の審査員になる
M‐1の本質とは?
「ボケとツッコミ」の〝実験場〟と化したM‐1
キャラクターのショーケースとしてのM‐1
ひな壇番組の意味
3 2000年代の「お笑いビッグ3」、それぞれの道
さんまとM‐1
さんま、「お笑い怪獣」になる
孤高の存在となったさんま
「武」と「たけし」の〝ふれ幅〟効果
「くだらなさ」の美学とその行方
散歩する趣味人・タモリ
〝理想の大人〟となったタモリ
2010年代に向けて
第4章 笑いの新たな潮流
1 お笑い芸人とユーチューバー──ネットの笑いはヌルいのか?
お笑い芸人は知的?
〝芸人至上主義〟の背景
ユーチューバーの台頭
お笑い芸人 vs. ユーチューバー
「ヌルさ」の意味
〝二刀流〟芸人の登場──テレビからYouTubeへ
2 「お笑い第7世代」と「やさしい笑い」
M‐1の復活
霜降り明星、そしてぺこぱのM‐1
「お笑い第7世代」の誕生
お笑い第7世代と「卒‐ダウンタウン」
「やさしい笑い」の時代──さんまからサンドウィッチマンへ
3 「肯定する笑い」の時代へ
漫才ブームの歴史的意味
「一億総中流」意識の揺らぎ
オタクの大衆化
テレビと社会のずれ、それに伴う笑いの変容
「相互性の笑い」という新潮流
テレビとネットを横断するフワちゃん
「子ども」という戦略
他者を肯定する笑い
最終章 「笑う社会」の行方──「お笑いビッグ3」が残したもの
「あれは漫才なのか」論争
「漫才に定義はない」
上書きれた漫才の歴史
「お笑いビッグ3」から「お笑い第7世代」へ
あとがき
参考文献一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ykmmr (^_^)
ホークス
緋莢
ライアン
スプリント