- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
量的・質的金融緩和(QQE)、マイナス金利、イールドカーブ・コントロール、そしてコロナショック……。2015年3月から2020年3月までの5年間、著者は黒田総裁下の日本銀行で、金融政策を決定する政策委員会審議委員を務めた。2%の物価目標とデフレ脱却に向け、日銀はいかに苦闘したのか。さまざまな批判に何を思い、反論したのか。アベノミクスと金融政策決定の舞台裏を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
OK
3
「1980年代までの3%成長に比べれば、経済停滞は今も続いていると言える。成長率が下がること自体は不思議でも何でもない。貧しい国は豊かな国の制度、技術、文化を真似ることができる。自ら技術革新を行うより、真似る方が簡単である。だから、貧しい国は真似ることによって豊かな国よりも高い成長を続けることができる。しかし、そうできるのは貧しいうちだけだ。豊かな国に追いつけば、真似るものがなくなって、豊かな国と同じだけしか成長できなくなる」2022/09/24
aun
3
日銀シンパなので全く響かなかった。筆者らリフレ派はあれだけ量を増やせばインフレを起こせると主張していたのに結局うまくいかず、それをなぜか雇用は確かに改善したと論点をずらして自らを擁護している。本当に身勝手。また、何度も「高偏差値」との表現が登場し、いい年した大人が偏差値を気にする様子が滑稽であった。未曽有の金融政策の行方について全く触れない(あえて?)のは日銀の意思決定を担った立場として無責任と言わざるを得ない。2021/09/21
okadaisuk8
2
リフレ派経済学者が日銀審議委員時代の経験をまとめた著作。内容は親分・岩田規久男前副総裁の回顧録と近く、文章が軽妙で読みやすいのも共通する。米国では左派こそ金融緩和を唱えているのに、日本では安倍氏への反感からかリベラルメディアが緩和に批判的と指摘していると指摘し、常々私も不思議に思っていたので、共感した。2%目標が未達でも雇用回復したし批判しなくてもいいじゃんという主張も含め、とても合理的・実利的な考え方が記されている。一方、これだけ緩和をしても物価上昇など思い描いた形にならないことへの説明は不足気味。2022/09/20
tacacuro
1
金融政策を巡る議論はもちろん、日銀の舞台裏や日本経済社会政治論、経済企画庁OB列伝、MMTの解説など幅広く多岐にわたる内容が一冊に一杯つまっていて、とてもぜいたくな本。「500兆円しか貸出先がないのに、800兆円も預金を集めている」銀行こそ、まずは構造改革が必要だという。そして「規制改革や構造改革には、リーダーの断固とした意志とともに、人手不足が必要」だと。全体的に歯に衣着せぬ論調で、わかりやすくて心地よい。2021/07/21
*おきた
0
経済に明るくないからイマイチ分からないけれど、とりあえず金融緩和したかったのね。 昔からしたかったのに、人に納得してもらえんくて実現できてなかったみたい。当時に出来てたらもっと崇められてたかもしれないね。 上手いこと出来たなぁみたいな感じだったけど、小市民の自分にしてみれば、あんまり個人の生活は変わんねえや。 経済学者の自己主張と政策史の私的回顧と言う風にかんじたかな。2025/08/08
-

- 電子書籍
- 君は春に目を醒ます 9巻 花とゆめコミ…
-
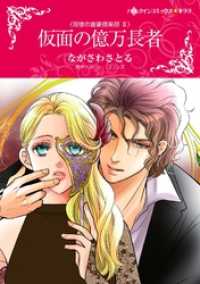
- 電子書籍
- 仮面の億万長者〈背徳の富豪倶楽部 II…
-
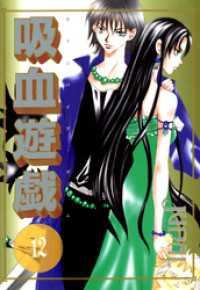
- 電子書籍
- 吸血遊戯<ヴァンパイア・ゲーム>(12…
-

- 電子書籍
- リッツ・カールトン 至高のホスピタリテ…





