内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
数ある日本の祭の中でも独特の熱狂を帯びる地車(だんじり)。天神祭をはじめ大阪の夏祭で育まれた神賑(かみにぎわい)の祭具である地車のルーツを解く鍵は、江戸期に淀川を往来した豪華な川御座船とニワカと呼ばれる滑稽寸劇にあった。岸和田をはじめ大阪(摂河泉)から瀬戸内沿岸一帯へと、広く西日本に展開する地車文化を、歴史史料・形態・彫刻・囃子などから多角的に描き出す初の書。貴重写真・オリジナル図版を多数収載。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
1
地車に残る御座船の記憶2021/11/08
ポルポ・ウィズ・バナナ
1
◎「神事」と「神賑行事」を分けるという発想、白眉だなと思ったら成る程、著者は岸和田出身。だんじり祭りはヒトの意識がカミに向いている神事ではなく「神賑行事」でありヒトの意識はヒト(氏子同士や見物人)を向いているとある。◎だんじりは船の見立てだが、それはなぜか「船体」を付けなかった──これも面白い。そうみるとだんじりのビジュアルがかなり滑稽に映る。◎そもそも疫病含む罪穢を祓う神事が神賑行事として自己目的化しコロナ禍においてさえ祭りを強硬するサマはまあまあ地獄2021/08/28
Go Extreme
1
地車の誕生: 江戸時代の御座船 祭の中の御座船 地車と和船 ニワカ(俄)と地車の舞台 地車の誕生 地車誕生の時期 ダンジリの語源 地車の隆盛: 大坂の夏祭 町奉行からの例触 地車の実態 車の担い手 催太鼓と地車の分別 橋と地車 天神祭 地車の宮入り台数の変化と社会背景 明治時代の大阪の地車 地車の展開: 地車の基本仕様 地車の伝播 地車の展開 船型地車 地車の形態に類似する祭具 神賑の民俗学: 神賑の定義 神賑の語誌 神賑の民俗学2021/08/08
-

- 電子書籍
- ANGEL(分冊版) 【第60話】 ぶ…
-

- 電子書籍
- 復讐の赤線~恥辱にまみれた少女の運命~…
-
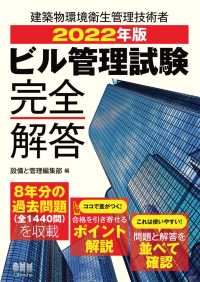
- 電子書籍
- 2022年版 ビル管理試験完全解答
-
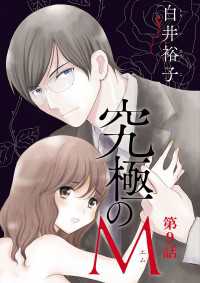
- 電子書籍
- 究極のM【分冊版】 9 A.L.C. …
-
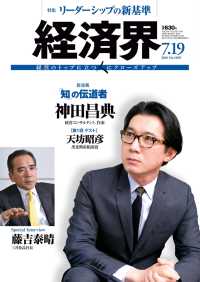
- 電子書籍
- 経済界2016年7月19日号




