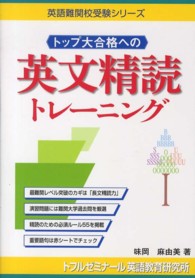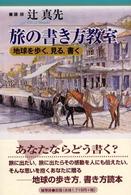内容説明
トーマス・クーンという名前を知らない人でも、また科学史や科学哲学などの分野に縁のない人でも、「パラダイム」という言葉なら聞いたことがあるに違いありません。
いまや日常語として「物の見方」「考え方の枠組み」の意味で使われているこの言葉は、もともと1962年刊『科学革命の構造』というクーンの著書の中で語られたもので、「一定の期間、研究者の共同体にモデルとなる問題や解法を提供する一般的に認められた科学的業績」を意味していました。
この概念は、それまでの「科学革命は17世紀に起きた1回きりの大事件」という科学史の常識を覆す衝撃的なもので、「<科学>を殺した」といわれたほど、大きな影響を及ぼしました。
パラダイム・シフトは歴史上何回も起こり、それは社会・文化の歴史と密接な関係があるとするクーンの見方は、フーコーが人文科学的知の布置の変化を考古学的方法によって解き明かしたと同じスタンスで、「知」の連続的進歩という通念を痛撃しています。
本書は二十世紀終盤の最大のキーワードとも言うべき「パラダイム」の考え方を面白く、わかりやすく説くものです。
●主な内容
第1章 <科学>殺人事件
第2章 科学のアイデンティティ
第3章 偶像破壊者クーンの登場
第4章 『科学革命の構造』の構造
第5章 パラダイム論争
第6章 パラダイム論争の行方
【原本】
『現代思想の冒険者たち クーン パラダイム』1998年 講談社
目次
第1章 <科学>殺人事件
第2章 科学のアイデンティティ
第3章 偶像破壊者クーンの登場
第4章 『科学革命の構造』の構造
第5章 パラダイム論争――<科学>殺人事件の法廷
第6章 パラダイム論争の行方
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
逆丸カツハ
空虚
Olive
ハチアカデミー