- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
物事を現実とは異なるゆがんだかたちで認識してしまう現象、バイアス。それはなぜ起こるのか、どうすれば避けられるのか。本書では、現実の認知、他者や自己の認知など日常のさまざまな場面で生じるバイアスを取り上げ、その仕組みを解明していく。探求の先に見えてくるのは、バイアスは単なる認識エラーではなく、人間が世界を意味づけ理解しようとする際に必然的に生じる副産物だということだ。致命的な影響を回避しつつ、それとうまく付き合う方法を紹介する画期的入門書。
目次
まえがき
第1章 バイアスとは何か
1 認知とそのゆがみ
認知とは何か
ゆがみとは何か
認知の脳内処理
自由エネルギー原理による説明
抽象的なものの認知のゆがみ
他者の観察におけるゆがみ
2 バイアスはなぜあるのか?
合理的判断を邪魔するバイアス
ゆがんだ認知のメリット
ゆがんだ認知は受け継がれてきた
生き残りマシンとしての生物
生き残りに必要な要素
物理的環境への適応
対人関係的(社会的)環境への適応
二つの環境で生き延びた
心の働きのばらつきは、遺伝子のばらつきから
進化とバイアスの関係
すばやく情報を処理するメリット
ヒューリスティックスの重要性
3 バイアスについて知る意義
バイアスは無意識に生じるもの
バイアスかもしれない、と思うことの効果
バイアスを意識的に検討する
第2章 バイアス研究の巨人──カーネマンとトヴァースキー
1 見え方の違いと意思決定
プロスペクト理論──喜びと悲しみの非対称性
不確実性下の意思決定
フレーミング効果──「朝三暮四」は笑えない?
2 数字の影響力
係留と調整のバイアス──アンカーは重い
司法判断におけるアンカー
基準率の無視──確率は難しい
3 ヒューリスティックスによる判断
代表性ヒューリスティックス──「っぽさ」で判断する
リンダ問題──確率的には真逆なのに……
連言錯誤はなぜ起こる?
ギャンブラーの誤謬──ずっと表なら次は「裏」?
「小数の法則」
「ホットハンド」の錯覚
シミュレーション・ヒューリスティックス──「もし、こうでさえなかったら」
反実仮想と反実感情
第3章 現実認知のバイアス
1 情報選択のバイアス
現実を認識する枠組み
確証バイアス──「私の正しさは証明された」
確証バイアスの実験例
その事例は一般的か?
四枚カード問題
2 知識という呪縛
後知恵バイアス──「そんなこと、聞く前から知っていたよ」
バーナム効果──「やっぱり占いは当たる!」
なぜ当たらない性格診断を信じてしまうのか
ポジティブ幻想と楽観バイアス──「自分だけは大丈夫」
正常性バイアス──「今は緊急事態ではない」
3 偏見を生み出すバイアス
外国人犯罪は本当に多いのか
錯誤相関──目立つものどうしは結びつく
少数派を悪い人びとだと感じるわけ
第4章 自己についてのバイアス
1 自分を認識する枠組み
自己を認知するということ
性格とは何か
2 自分はいいものだというバイアス
自己高揚動機
抑鬱者のセルフ・スキーマ──否定的に自分を認知する
スキーマが認知を左右する
スキーマの揺らぎによる混乱──学校スキーマ
セルフ・ハンディキャッピング──本当は自分はもっとできる
スポットライト効果──自分は見られている
透明性錯誤──自分の内心はバレている
視点取得の難しさ
3 自分は正しいというバイアス
自己中心的公正バイアス
社会的妥当性と自己確証動機
合意性バイアス
セルフ・サービング・バイアス
認知的不協和との類似点
第5章 対人関係のバイアス
1 対人認知のバイアス
期待効果──期待が人物認知をゆがめる
対人認知での確証バイアス
基本的帰属の誤り
一貫性バイアスと暗黙の人格理論
ネガティビティ・バイアス
ミスアンスロピック・メモリー
パーソン・ポジティビティ・バイアス
2 見た目と特性
ハロー効果──見た目よければすべてよし
ベビーフェイス効果──童顔は守りたくなる
見た目から社会経済的地位を推測する
外集団等質性バイアス
私たちに潜む人種のバイアス──記憶が変容する
偏見とバイアスの違い
3 人種と法執行のバイアス
射撃者バイアス
目撃証人の自己人種バイアス
カメラ・パースペクティブ・バイアス
人種と死刑判決
刑事事件における判断への容姿の影響
バイアスと冤罪
第6章 改めて、バイアスとは何か
1 バイアスはなぜ存在するのか
バイアスは認知のゆがみ
バイアスがあるのは生き残りのため
2 バイアスを緩和する方法
バイアスからは逃れられないのか?
意思決定の誤り?
人間の記憶と機械の記録
後知恵バイアスと記憶の書き換え
後知恵バイアスの緩和策
係留と調整のバイアスの緩和策
裁判におけるバイアスの緩和策
確証バイアスの緩和策
集団で話すことによる緩和策
ゲームや説明ビデオを用いた緩和策
3 バイアスから逃れるべきなのか?
人間機械論
意味の世界で生きる
心理学に意味を取り戻す
意味を紡ぐ存在としての人間
たとえバイアスがあったとしても
あとがき
参照文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
あおでん@やさどく管理人
おせきはん
テツ
紫の煙
-
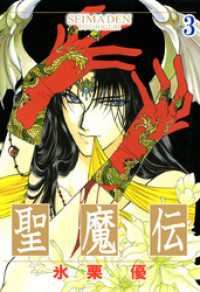
- 電子書籍
- 聖魔伝(3) まんがフリーク
-
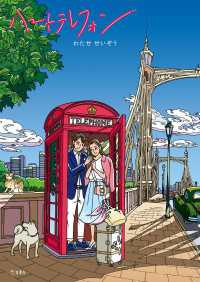
- 電子書籍
- ハートテレフォン 立東舎
-
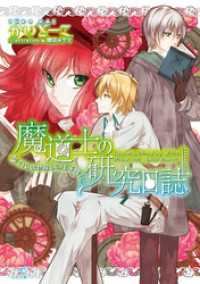
- 電子書籍
- 魔道士の研究日誌 2 召しませ愛しの王…
-
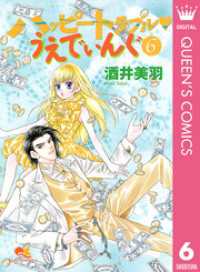
- 電子書籍
- ハッピートラブル・うえでぃんぐ 6 ク…
-
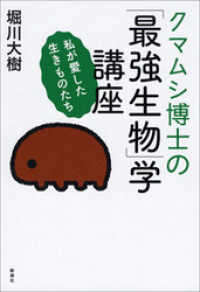
- 電子書籍
- クマムシ博士の「最強生物」学講座―私が…




