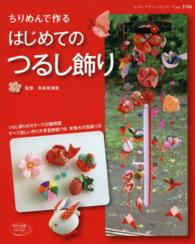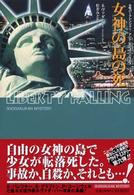内容説明
GAFAにデータと富が集中している。彼らはSNS事業者としての「表」の顔で集めたデータを、「裏」の広告事業で活用して利益を上げている。一流企業から中央省庁まで貴重なデータを彼らに無償で提供してきた。
日本がそれを易々と許した一因に、にわかに信じがたい法制度の不備がある。彼らの急速な進化に国内法が追いつかない。ヤフーや楽天に及ぶ規制も、海外プラットフォーマーは対象外という「一国二制度」が放置されてきた。GAFAはこの「グレーゾーン」を突き進む。
またEUに比べて遥かに弱い競争法やプライバシー規制、イノベーションを阻害する時代遅れの業法……。霞が関周辺にはそれらに気づき、抗おうとした人々がいた。本書はその闘いの記録であり、また日本を一方的なデジタル敗戦に終わらせないための処方箋でもある。最前線で取材し続ける記者がデータプライバシーに無頓着な日本へ警鐘を鳴らす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
45
読売新聞記者による海外PF事業者への日本の政策対応の遅れを指摘する憂国の書。役人が苦手とする、新たな政策分野で省庁を跨がる問題であった事が初動の遅れの主因であったと理解したが、海外事業者に対する法施行に係る意識が欠如していた点や、課徴金制度に係る内閣法制局の慎重な姿勢なども指摘する。数少ない心ある研究者、弁護士、政治家、役人にも光を当てている点は、取材源を基に論理構成する記者としては当然ではあるが、同時に著者のような例外を除いたメディアの消極姿勢も指摘すべきと思われる。3年前の本だが、続編が読みたくなる。2024/06/20
kei-zu
17
本書は、単にGAFAの巨大化に警鐘を鳴らすものではない。我が国のデジタル行政とそれへの課題解決に向けて関係者が必死に対処しようとした記録でもある。 法的な共生によらない指導の効果が国外業者へ限定的である一方、法的な規制は経済界から反発を招くことになったという。 そのような状況の中で、専門的な知見のもと、議論を積み重ね対応を図っていこうとする関係者の行動は読んでいて心づいよい。 そして、その「闘い」は、現在進行形でもあるのだ。 ネット行政に調味ある方は、ぜひ目を通してほしい。2021/07/05
ザビ
11
Gメールの連動広告配信はOKなのに、国内事業者ヤフーメールの連動広告配信はNG。そんな理不尽な国の判断が現実にあったことにビックリした。その根拠は「日本国内にサーバーを持たないので我々は日本の電気通信事業者ではない」、つまりGoogleは日本の法律の適用外だと自ら主張し、総務省も2014年の政府答弁でそれを認めたという。ITで軽々と国境を超えて日本で商売してるのに提供サービスは国内法で規制されないGoogleと、片や法規制を受ける日本企業という矛盾が続いたのが2010年代。動画配信は著作権法(文化庁)、2023/12/19
Yuichi Tomita
5
これは面白かった。GAFAを中心とするプラットフォーマーがどれだけ力を持っていて、いかに日本が舐められているかがよくわかる。それに加えて、海外企業がいかに野放しにされてきたかも。 記述は、広告や検索に関するものが多く、必然的にGAFAのなかでもGoogleとFacebook(Meta)が多い。 テーマはかなり広いが、19年、20年辺りに公取、総務省、経産省から出た報告書の背景がよく分かる。2022/07/05
TK39
4
GAFAとの闘いとのタイトルだが、内容はいかに日本の省庁がプラットフォーム、個人情報対応で後手を踏んできたか?について。グローバル化の時代に日本企業への規制だけに目を配り、米国の圧力を恐れ、GAFA規制は甘い。これも日本の官公庁が法律の専門家のみで運営され、技術者はいないことが原因か?デジタル庁には期待したい。しかし、日本のIT企業の様にいつまでモノを売る企業を守る必要があるのか?ベンダーロックを間接的に官公庁が支援するのは良くない。彼らはソフトウェア産業にはなれない。2021/06/20
-

- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2014年 3…