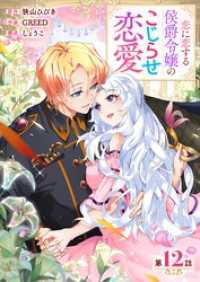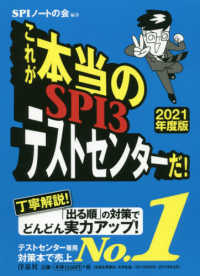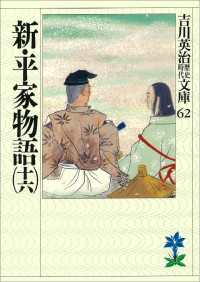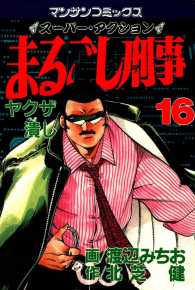内容説明
個性の強い子どもたち。突出した才能に恵まれても、いくらかは問題児扱いされて居場所を失い、結果として不登校になりがちだ。そんな彼らに学びの場を提供するのが東大先端研「異才発掘プロジェクト」で、そこでディレクターを務めるのが中邑教授である。「成績が良ければ優秀」な時代は過ぎた? 学校や親が子どもとの間に築いた“壁”を越える方法とは? 「全ては見守ること」という主張や最先端の研究の場で得られた知見を一冊に集約し、子どもの才能を伸ばす子育て法を伝授。今こそ、仲間外れの先に広がる可能性に向き合え!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン
27
偏った平等観、横並び思考の中でも優越感を持ちたい心。小さなひずみが積み重なって、大きな災害やコロナ禍の中の世論、大人たちの大人げない言動を通して表面化、可視化されてきている気がします。考える視点をたくさんいただけました。2021/08/01
りょうみや
24
最初に様々な個性的、今の社会では問題児に見なされることが多い子供たちの事例。そして親や社会の画一的な価値観が子供も親も苦しめていることを説明。著者の異彩発掘プロジェクトで変わっていった子供たちも紹介。親として子供にできることは結局は自分の枠を広げて見守って待つことになる。2022/03/11
みっこ
17
不登校の子どもたちに向け、型にはまらない学びを提供するプロジェクト《ROCKET》を運営している教授が書いた本。仕事柄さまざまな個性を持つ子と接する機会があるけど、たしかに特性が強い子を標準教育に当てはめるのは無理があると思う。もっと柔軟に個別の対応ができれば、ずっと生きやすくなるはずなのに。《ROCKET》の教育内容はとても魅力的でした。こういう考え方がもっと浸透してほしい。2025/02/28
み
16
学校の壁を越える「異才発掘プロジェクトROCKET」の取り組みが面白いと感じた。自身が小学校教員なのもあって、学校からの目線で読んでいた。例えば、学習指導要領に書かれていること(もっと楽に言えば教科書で取り上げられている内容)は必ず全員に学ばせなければとか、限られた時間内でどう終わらすかとか、子ども一人ひとりが違うのも分かった上で、授業には必ず目標があって評価をしなければとか。だがそれが合わない子が必ずいる。どこかに旅に出て遠さを実感したり500円限定で豆料理を買ったりで学べることもある。2021/08/10
大先生
9
東大で「異才発掘プロジェクトROCKET」を推進されている教授の本です。【子育てで重要なことは「見守ること」。子どもには、それぞれ個性があり、受験勉強に向いている子もいれば、そうでない子もいる。親心といいつつ、親が子どもの才能を潰す壁になっていることが問題。人と違うからといってすぐ発達障害にしてしまう風潮にも疑問がある。今こそ親馬鹿の壁を越えていけ】子育てに正解はなく、褒めることも、叱ることも必要なわけです。他の子と比べて、親が不安になるのは当然ですが、それでも余計な干渉をせず見守り続けることですね。2025/01/22