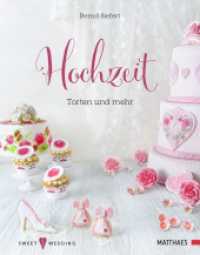内容説明
昭和初期の小作争議が頻発した時代,農政官として出発した柳田は,農村の疲弊と農民の貧困を,農村内部の問題としてではなく,都市との関係でとらえた.田舎から都市への人の流入を歴史的にたどり,文化全体をみつめるなかで,具体的な希望として農民による協同組合運営を提言.現代においても示唆に富む一書.(解説=赤坂憲雄)
目次
自序┴第一章 都市成長と農民┴一 日本と外国との差┴二 イナカと田舎┴三 都とその他の都市┴四 城下町の支持者┴五 村の市と町の常見世┴六 町人の故郷も村┴七 土を離れた消費者心理┴八 宿駅生活の変化┴九 愛郷心と異人種観┴一〇 農村から観た都市問題┴第二章 農村衰微の実相┴一 村と村との比較から┴二 生活程度の高下┴三 物議と批判力┴四 一人貧乏と総貧乏┴五 農だけでは食えなくなる┴六 不自然なる純農化┴七 外部資本の征服┴八 農業保護と農村保護┴九 生計と生産┴一〇 人口に関する粗雑な考え方┴第三章 文化の中央集権┴一 政治家の誤解┴二 都市文芸の専制┴三 帰化文明の威力┴四 そそのかされる貿易┴五 中央市場の承認┴六 無用の穀価統一┴七 資本力の間接の圧迫┴八 経済自治の不振┴九 地方交通を犠牲とした┴一〇 小都市の屈従摸倣┴第四章 町風・田舎風┴一 町風の農村観察┴二 田園都市と郊外生活┴三 生活様式の分立┴四 民族信仰と政治勢力┴五 自分の力に心付かぬ風┴六 京童の成長┴七 語る人と黙する人と┴八 古風なる労働観┴九 女性の農業趣味┴一〇 村独得の三つの経験┴第五章 農民離村の歴史┴一 都市を世間と考えた人々┴二 商人の根原┴三 職人の都市に集まる傾向┴四 武士離村の影響┴五 長屋住居の行掛り┴六 冬場奉公人の起り┴七 越後伝吉式移民┴八 半代出稼の悲哀┴九 紹介せられざる労働┴一〇 住所移転の自由不自由┴第六章 水呑百姓の増加┴一 分家は近代農村の慣習┴二 家の愛から子の愛へ┴三 下人は家の子┴四 年季奉公の流行┴五 いわゆる温情主義の基礎┴六 地主手作の縮小┴七 農作業の繁閑調節┴八 大田植の光景┴九 多くの貧民を要した大農┴一〇 親方制度の崩壊┴第七章 小作問題の前途┴一 地租条例による小農の分裂┴二 小作料と年貢米┴三 たった一つの小作人の弱味┴四 耕作権の先決問題┴五 土地財産化の防止策┴六 地主の黄金時代┴七 地価論に降参する人々┴八 土地相場の将来┴九 挙国一致の誤謬┴一〇 農民組合の悩み┴第八章 指導せられざる組合心┴一 二種の団結方法┴二 組合と生活改良┴三 産業組合の個人主義┴四 農民組合の個人主義┴五 組合は要するに手段┴六 農民の孤立を便とする階級┴七 前代の共同生産┴八 山川藪沢の利┴九 土地の公共管理┴一〇 地租委譲の意義┴第九章 自治教育の欠陥とその補充┴一 村を客観し得る人┴二 保護政策の無効┴三 都市の常識による批判┴四 人量り田の伝説┴五 村統一力の根柢┴六 平和の百姓一揆┴七 利用せらるる多数┴八 古風なる人心収攬術┴九 自尊心と教育┴一〇 伝統に代る実験┴第一〇章 予言よりも計画┴一 三つの希望┴二 土地利用方法の改革┴三 畠地と新種職業┴四 中間業者の過剰┴五 不必要なる商業┴六 消費自主の必要┴七 都市失業の一大原因┴八 地方の生産計画┴九 都市を造る力┴一〇 未来の都市の本務┴解説 失われた共産制の影を探して(赤坂憲雄)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
うえぽん
roughfractus02
うえ
しゅう
-
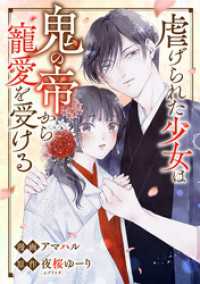
- 電子書籍
- 虐げられた少女は鬼の帝から寵愛を受ける…