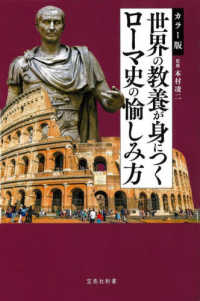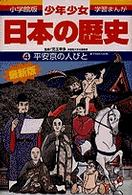内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
映画はもはや、映画館で「注視」することが主流の視聴モードではない。一回性は失われ、いつでも繰り返して観ることが可能になった。さらには「ながら見」や移動中など、「気散じ」的な視聴モードも一般化し、映画の時間・空間は、その構造の変化を余儀なくされている。いま、映画はどう論じうるだろうか。
映画の誕生からその文法までを丁寧に紐解き、さまざまな映像表現を真摯に見つめ、フレームの奥深い内部だけでなく、フレームの外部や裏側まで思考を重ねる。映像表現の醍醐味に光をあてなおす、まったく新しい映像論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
14
映画における、構図・編集などの技法を実際の映画(多くが古典)の分析を通して伝える。音響の使い方とアニメーションの技術に比較的多くのページを割いている。監督のいわゆる「作家性」が、どのような技法から作られていくのかを記述していて面白い。川島雄三の人・物を真ん中おいて会話する二人を「分裂」させる構図、黒澤明の対位法的音楽の使い方、新海誠の「線」。映画が一体何をやっているか。そのことをまず把握できる一冊。面白く読んだ。2022/03/29
gu
7
とても勉強になった。メディアミックス、ネット配信、劇場のアトラクション化といった現代の視聴形態の批評であり、それらを用いた現代における映画批評である。繰り返し見た上での詳細な分析が今は可能なのだから覚えてる限りがその作品だとはもう言えない。以前読んだ『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(細馬宏通)を思い出すところもあり。2022/12/13
あんすこむたん
6
カメラワークを意識して映画映像作品を見るなら、必須の書。アニメ作品やアダプテーションにも触れているので、幅広く役立つように思えた。2021/10/06
かいこ
5
映画のフォルマリズム分析の手法一覧という感じ。読んでて普通に面白いけど、それ以上に勉強になるという印象。比較的小粒の分析が多かったけど、キューブリックの『シャイニング』の章は纏まってて面白かった2021/12/26
kentaro
4
教科書、しかし退屈しない教科書。2021/05/20