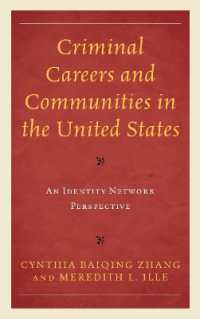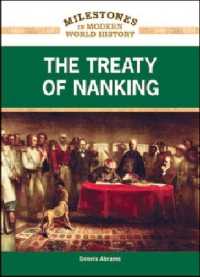内容説明
なぜ他のものは捨てられても、
天皇制だけは捨てられないのか?
悠久の謎の根幹に挑む。
天皇とは何か。天皇制は何のために存在しているのか。天皇の家系は、どうして他の家系と比べて特別に高貴なのか。
こうしたことを誰にも納得できるように説明することは、とてもむずかしい。だがいかにむずかしいとしても、天皇制こそが、日本人である「われわれ」は何者なのか、を理解する上での鍵なのだ。
天皇制の過去、現在を論じることを通じて、日本人とは何か、日本社会の特徴はどこにあるのかを探究する刺激的対談。社会学者と憲法学者が、誰もが答えられない天皇制の謎に挑戦する。
天皇制を理解することは、日本社会の中のひとつの政治制度や特殊な文化様式を理解すること(に尽きるもの)ではない。天皇制を見ることは、結局、日本人と日本社会の歴史的な全体を見ることに直結している。──大澤真幸
天皇制は、天皇・皇族にとっても、日本社会にとっても犠牲が大きく、他方で、それが果たしている法的役割も国民の関心も低い。この制度が存在すること自体が最大の不思議だと言わざるを得ない。──木村草太
【目次】
第1章 現代における天皇制の諸問題──象徴、人権、正統性
第2章 歴史としての天皇制──上世、中世、近世まで
第3章 近代の天皇制──明治維新から敗戦まで
第4章 戦後の天皇制──憲法、戦後処理、民主主義
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こーた
219
謎のシステムの周縁をウロウロする小説、というのに目がなくて、たとえばレム『ソラリス』とかカフカ『城』とかがそうなのだけど、妖しさに惹かれてつい読んでしまう。天皇制はこの実社会にいまも存在する謎システムだ。その謎が社会全体を支えている(かもしれない)という意味で最大の謎といっていい。はっきりいってむずかしい(本自体の語り口はやさしく読みやすいけれど)。むずかしいということがよくわからないくらい、天皇制はむずかしく、しかも解いてしまったら機能しなくなる怖れさえはらむ。そんな奇妙な謎を、社会学者と憲法学者が⇒2021/09/28
trazom
106
今年読んだ中で一番面白い一冊だった。木村先生は聞き手に徹し、大澤真幸先生の独壇場。天皇制を切り口にするが、議論は、社会学、日本史、西洋・東洋の政治学・哲学などに大きく翼を広げ、大澤社会学の広さと深さが満喫できる。天皇制に関しても、「天皇が象徴」いう条文は規範か事実か、象徴と代表の違い、天皇の積極的機能と消極的機能、万世一系というフィクション、天皇制の文化財的価値、国民主権のリザーブとしての天皇など、これまで気づかなかった論点を教えられる。天皇とは「シニフィエなきシニフィアン」という表現がなるほどと思える。2021/08/11
アキ
99
天皇とは憲法上で日本国の象徴とされているが、なぜ天皇制がこれまで維持されてきたのかは誰も説明できない。憲法学者と社会学者の対談は刺激的で考えさせられる。そもそも天皇と呼ぶようになった聖徳太子の時代から、絢爛たる源氏物語の主人公は天皇家であったが、鎌倉時代に承久の乱で武士が権力を持ち、江戸時代には極貧で存在も薄かった。それが明治維新で錦の御旗で祭り上げられ、憲法上現人神になり、終戦後人間宣言した。木村は、江戸時代の天皇を「ノンアルコールビール」、明治政府にとっては「アイロニカルな没入」、現行制での天皇制は→2021/10/02
ころこ
39
今までは橋爪大三郎とつくってきたシリーズを、今回は木村を対談相手として行っています。恐らく大澤には結論があって(〈世界史〉の哲学を連載しているので)、橋爪だとそれを強化することにしかならないが、あえて畑違いの木村にしています。その配慮は冒頭第1章と最後の第4章という木村が入って来やすい話題を重要な個所に割り当てていることにみられます。大澤が「第三者の審級」を木村に説明している箇所が第2章にあります。木村も実は理解しているが、あえて大澤に基本的な質問を投げ掛け、改めて最初から本書独特の新しい表現で説明してい2021/08/25
原玉幸子
23
「天皇制は政治的概念」と認識している私には、歴史的に振り返る第2章以降で、へぇーっと驚く史実は無かったものの、例え話然り「消極的機能」、「アイロニカルな没入」等の用語で「天皇制はこうやって切り取るんですよ」と、私の漠とした思いを小気味のよい対話で解き明かし、右翼から脅される様な言質は微妙に(学術的に!)避けている二人の手法が知的に面白く、成程と感心しました。天皇制が無くなって日本が崩壊する危うさを一番真剣深刻に感じているのは、(痛烈な皮肉な気もしますが)国民でなく天皇本人だったりして…(◎2021年・夏)2021/07/08