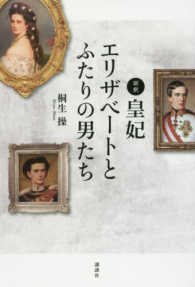内容説明
元国税調査官が読み解く「日本国の決算書」!
大化の改新、鎌倉幕府の誕生、応仁の乱、戦国時代の終焉、
明治維新、太平洋戦争、高度成長時代、失われた30年……
帳簿から見えてきた、「あの大事件」の真相。
なぜ、織田信長は戦場で「領収書」を発行したのか?
ビジネスマンの頭にスッと入る、まったく新しい「歴史教科書」が登場!
【目次】
第1章 大和朝廷は会計力で国を統一した
第2章 坊主と武士は勘定に強かった
第3章 戦国時代の会計革命
第4章 江戸時代の優れた会計官たち
第5章 明治維新の収支決算
第6章 会計から読み解く戦前社会
第7章 高度成長とバブルの会計事情
第8章 平成“失われた30年間の会計内容
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
42
著者は元国税調査官の大村大次郎氏。会計的視点で日本の過去から現在まで読み解く、今までにないアプローチで面白かったです。大和朝廷の時代にすでに全国一斉の国勢調査を6年ごとに実施。武田信玄が統治していた甲斐の税は農地ではなく家屋や家族に課税していた(山間部のため農地が少なかったから)。武闘派のイメージの加藤清正も石田三成と同じ会計官だった。江戸時代の近江商人は複式簿記を使っていて、現代の世界標準に近い会計方式を駆使していた。江戸中期の財政は厳しく、貨幣の改鋳関連による収益に頼っていた。2021/08/01
いーたん
28
会計の視点で日本の歴史を解説。目からウロコのエピソードが満載。これまで何冊か著者の本を読んだがどれも面白くタメになった。本書も期待通り。正倉院展でもキレイな楷書で納税状況が書かれた巻物があったけど、奈良時代は高度な税収システムだったそう。それでも時間が経つと、税の徴収者が私腹を肥やし制度が崩壊してしまう…とか、珍しい布製のお札の西郷札、満州事変が起こる背景にも驚いた。ライブドアは嵌められたとか、わかりやすく書かれてある。ただ、財閥の中で、「三井商事」とあるのがどうにも解せなくて…昔は商事だったのか?2021/05/27
MAEDA Toshiyuki まちかど読書会
12
備忘録 「国民の収入が増えれば、経済はよくなる」という思想で1960年に策定された所得倍増計画! 平成の失われた30年の理由は簡単「サラリーマンの給料が上がってないから」 一方、企業の内部留保は10年連続で過去最高更新し500兆円!! 所得税は増税を繰り返し10% 2022/09/04
akane
9
日本の会計史を語るなら、楽市楽座を起こした信長は必ず出てくるだろうと思っていた。銅銭が枯渇して金銀を「貨幣」として用いたという彼の通貨革命は、とても興味深かった。また、近江商人の複式簿記(損益計算書・貸借対照表)、江戸時代の貨幣改鋳事情なども。昔、石ノ森章太郎の『佐武と市捕り物控』で貨幣改鋳を扱ったエピソードを読んだことがあり、思わぬ形で時代背景を知るきっかけになって、ちょっとびっくり。近代・現代の会計史は、直接私たちの生活にかかわりのある話なので、なかなかに胃が痛い思いだった。2021/08/28
みのくま
7
元国税調査官の著者が、古代から現代まで日本史を会計という観点から読み解く。加藤清正や西郷隆盛など武辺者の印象がある偉人達も実は会計官から身を立てている事など興味深い指摘が多々されている。身分制や世襲制が徹底された時代は、下級士族は唯一の能力主義であった会計官でのし上がった様だ。またバブルが破裂した後の日本企業は実は業績を伸ばしていた事も書かれており、会計視点からだとイメージがガラリと変わる。だが他方で違和感はある。会計は確かに見えなかった視点を導入できるがそれはあくまで正史の補完として取り入れるべきだろう2025/03/15
-
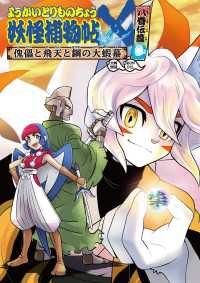
- 電子書籍
- ようかいとりものちょう19-妖怪捕物帖…
-
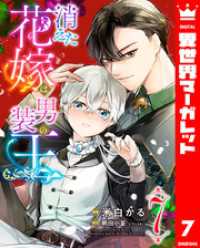
- 電子書籍
- 消えた花嫁は男装の王 7 異世界マーガ…
-

- 電子書籍
- 元カレの息子に一途に迫られてます【タテ…
-

- 電子書籍
- 処女仲介人~奪ってほしい女達20 CO…