内容説明
無線通信とレーダとの類似性の視点を取り入れながら,両者に共通のレンジ方程式,変復調方式,信号検出に特化し,それぞれに導入部として無線通信を専門とする人にとって馴染みのある内容を入れ,理論を解説した。
目次
1.レーダの概要
1.1 レーダの歴史
1.2 レーダの基本構成
1.3 レーダで推定可能なおもな物理量
1.3.1 目標位置の推定
1.3.2 相対移動速度の推定
1.4 レーダの種類
2.レンジ方程式
2.1 無線通信のレンジ方程式:フリスの伝達公式
2.2 レーダのレンジ方程式(1):孤立点目標のレーダ方程式
2.3 レーダのレンジ方程式(2):体積分布型目標のレーダ方程式
2.4 レーダのレンジ方程式(3):面積分布型目標のレーダ方程式
2.5 レーダのレンジ方程式(4):平均電力表現によるレーダ方程式
2.6 損失要因
3.アンテナ/受信雑音/レーダ断面積
3.1 アンテナ
3.1.1 開口面アンテナの概要
3.1.2 開口面アンテナの利得
3.1.3 開口面アンテナの放射指向性(1):方形開口一様分布
3.1.4 開口面アンテナの放射指向性(2):円形開口一様分布
3.1.5 開口面アンテナの放射指向性(3):円形開口ガウス分布
3.1.6 アレーアンテナの概要
3.1.7 アレーアンテナの放射指向性解析
3.1.8 リニアアレーの放射指向性
3.1.9 リニアアレーのグレーティングローブ
3.1.10 等振幅リニアアレーのアンテナ利得,サイドローブレベル,ビーム幅
3.1.11 平面アレーの放射指向性
3.1.12 4角配列平面アレーの放射指向性
3.1.13 任意周期配列平面アレーの放射指向性とグレーティングローブチャート
3.1.14 平面アレーのアンテナ利得
3.1.15 4角配列平面アレーと3角配列平面アレーの比較
3.2 受信雑音
3.2.1 受信系雑音源の概要
3.2.2 外来雑音電力(アンテナ受信雑音電力)
3.2.3 低雑音増幅器で発生する雑音電力
3.2.4 損失のある給電回路で発生する雑音電力
3.2.5 システム雑音温度
3.3 レーダ断面積(RCS)
4.変復調方式
4.1 変調波の表現式とアナログ変調
4.1.1 変調波の表現式
4.1.2 振幅変調
4.1.3 位相変調・周波数変調
4.2 無線通信におけるディジタル変調
4.3 レーダの変調方式概要
4.4 レーダの変調方式(1):パルス変調方式
4.4.1 送信波形と受信データ列
4.4.2 マッチドフィルタ(fasttime信号処理)
4.4.3 パルス変調信号のマッチドフィルタ
4.4.4 パルス変調信号の送信スペクトルと雑音帯域幅
4.4.5 ドップラー周波数が既知の理想的なマッチドフィルタ出力
4.4.6 ドップラーシフトが未知のマッチドフィルタ出力
4.4.7 パルス変調信号のアンビギュイティ関数
4.4.8 パルス変調信号に対するマッチドフィルタ処理後の信号対雑音電力比
4.4.9 ドップラー信号処理(slowtime信号処理)
4.4.10 離散フーリエ変換による損失(straddle損失)
4.4.11 ドップラー周波数による目標分離
4.4.12 PRFの選定方法
4.5 レーダの変調方式(2):線形周波数変調パルス方式
4.5.1 LFMパルス信号の送信波形
4.5.2 LFMパルス信号の周波数スペクトル
4.5.3 LFMパルス信号のアンビギュイティ関数
4.5.4 LFMパルス信号による距離応答特性
4.5.5 LFMパルス信号のドップラー応答とレンジドップラーカップリング
4.5.6 LFMパルスのマッチドフィルタ処理後の信号対雑音電力比とパルス圧縮利得
4.6 レーダの変調方式(3):符号位相変調パルス方式
4.6.1 2値位相変調:バーカー符号による位相変調
4.6.2 バーカー符号位相変調信号の周波数スペクトル
4.6.3 バーカー符号位相変調信号のアンビギュイティ関数
4.6.4 多値位相変調方式
5.信号検出
5.1 ディジタル無線通信における信号検出
5.1.1 熱雑音によるシンボル誤り率
5.1.2 フェージング環境下でのシンボル誤り率
5.2 レーダにおける信号検出の概要
5.3 複素ガウス分布不要信号に対する誤警報確率と変動のない目標の検出確率
5.3.1 誤警報確率としきい値の関係
5.3.2 検出確率としきい値の関係
5.3.3 ノンコヒーレント積分による検出確率向上
5.4 変動のある目標に対する検出確率
5.5 一定誤警報確率(CFAR)処理
5.6 CA-CFARの検出性能解析
付録
付録A 式(3.33)の導出
付録B 式(3.61)の導出
付録C 式(5.11)の導出
付録D 式(5.20)の導出
付録E 式(5.25)の導出
付録F 式(5.39)の導出
付録G 式(5.40)の導出
付録H 式(5.45)の導出
付録I 式(5.50)の導出
付録J 式(5.65)の導出
付録K 式(5.67)の導出
引用・参考文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
makio37
-

- 電子書籍
- 株式会社 神かくし 連載版 第74話 …
-
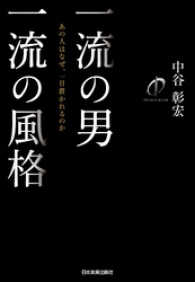
- 電子書籍
- 一流の男 一流の風格 あの人はなぜ、一…







