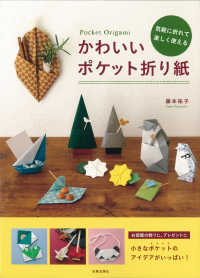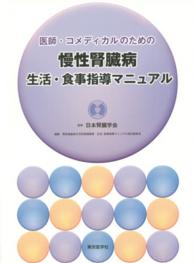内容説明
現在の計測の実情に合わせ,基礎的内容から最新のディジタル計測までを解説した教科書である。章末には課題を多く掲載し,理解度の確認・計算力向上ができるように工夫した。2019年5月から適用された新SIにも対応している。
目次
1.計測の基礎とSI
1.1 計測とは
1.2 計測の事例
1.2.1 天文と暦
1.2.2 クーロンの法則
1.3 次元と表記法
1.3.1 次元
1.3.2 量記号,単位記号の表記法
1.4 国際単位系(SI)
1.5 単位の例
1.5.1 メートル
1.5.2 秒
1.5.3 質量
1.6 電気量の標準と量子標準
1.6.1 電気量
1.6.2 量子標準
演習問題
2.測定手法と統計処理
2.1 直接測定・間接測定と偏位法・零位法
2.1.1 測定法
2.1.2 目盛
2.1.3 零位法
2.2 有効数字
2.3 不確かさと測定
2.3.1 不確かさ
2.3.2 測定と標準偏差
2.4 不確かさの伝搬
2.5 誤差
2.6 正規分布
2.6.1 ガウス分布
2.6.2 正規分布
2.6.3 標準偏差と不確かさ
2.7 最小二乗法
2.7.1 1変数最小二乗法
2.7.2 2変数最小二乗法
演習問題
3.雑音
3.1 デシベル
3.1.1 デシベルの定義
3.1.2 デシベルの演算
3.1.3 電圧を用いたデシベルの定義とdBm
3.2 熱雑音
3.3 ショット雑音,1/f雑音
3.4 外来雑音
3.5 SN比と雑音指数F
3.5.1 SN比の定義
3.5.2 雑音指数の定義
演習問題
4.演算増幅器とフィルタ
4.1 演算増幅器の原理と種類
4.1.1 演算増幅器とは
4.1.2 構成と特性
4.1.3 フィードバック
4.1.4 入力抵抗
4.2 演算増幅器を用いた各種回路
4.2.1 バッファ回路
4.2.2 加算回路
4.2.3 差動増幅回路
4.2.4 計装増幅回路
4.2.5 積分回路
4.3 フィルタ
4.3.1 フィルタの種類
4.3.2 一次低域フィルタ
4.3.3 二次低域フィルタと効果
演習問題
5.A-D変換器,電圧測定
5.1 A-D変換器の原理と種類
5.1.1 A-D変換器とディジタル
5.1.2 ビット数
5.1.3 二重積分方式(低速用)
5.1.4 逐次比較方式(中速用)
5.1.5 DR(デルタシグマ)方式(中速用)
5.1.6 内蔵用(中速用)
5.2 交流電圧の測定
5.2.1 可動鉄片型交流計器による測定
5.2.2 整流回路を用いた交流値
5.3 リアルタイムアナログ演算ユニットによる実効値の算出
5.4 基準電圧発生回路
演習問題
6.電圧型センサとマイコン計測
6.1 熱電対
6.2 ホール素子
6.3 温度IC
演習問題
7.電流測定
7.1 直流電流測定
7.2 微小電流測定
7.3 交流測定
演習問題
8.電流型センサを用いた光・放射線計測
8.1 フォトダイオード
8.2 光電子増倍管
8.3 放射線センサ
8.4 撮像素子
演習問題
9.抵抗,インピーダンス測定
9.1 間接測定と四端子法
9.1.1 抵抗の間接測定
9.1.2 ディジタルマルチメータによる抵抗測定
9.1.3 定電流回路
9.1.4 四端子法
9.2 高抵抗測定
9.3 ブリッジ回路とLCRメータ
演習問題
10.抵抗・キャパシタンス型センサ
10.1 ひずみゲージを用いた力センサ
10.2 白金測温抵抗体
10.3 サーミスタと光導電セル
10.4 キャパシタンス変化を利用した加速度センサ
演習問題
11.電力測定
11.1 直流電力
11.2 電流力計型計器
11.3 交流電力
11.3.1 交流電力の間接測定
11.3.2 3電圧計法
11.3.3 サンプリング法
11.3.4 ホール素子電力計
11.4 電力量計による測定
演習問題
12.周波数
12.1 セシウム原子時計
12.1.1 原子時計
12.1.2 周波数安定度と平均化
12.2 水晶振動子と周波数カウンタ
12.2.1 水晶振動子の構造と駆動回路
12.2.2 周波数カウンタ
12.2.3 ヘテロダイン
12.3 掛け算器と周波数の引き算
演習問題
13.オシロスコープ,記録計(ロガー)
13.1 オシロスコープの原理
13.1.1 アナログオシロスコープ
13.1.2 ディジタルオシロスコープ
13.1.3 入力プローブ
13.2 波形
13.2.1 波形の読み方
13.2.2 波形の用語
13.3 リサジューの図形
13.4 記録計
演習問題
14.コンピュータ計測とセンサ無線
14.1 計測ソフトウェア
14.2 センサ無線
14.3 センサネットワーク
演習問題
参考文献
演習問題解答
索引