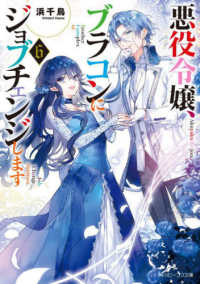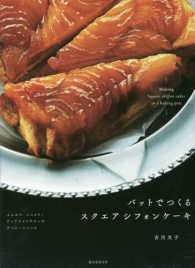内容説明
世界の孤児である私たちは、何らかの代補としての文字を必要とする。本書は、その様々な営為をふりかえる「文字の思想史」の試みである。
目次
はしがき
プロローグ:『アウト・サイダー』の世界
第I部 読み書きができるということ
第一章 現代社会におけるリテラシー問題:米仏の事例から
1 リテラシーとは何か
2 伝統的リテラシー:聖なるテクストを読むこと
3 スキルとしてのリテラシー
4 文化的リテラシー
5 リテラシー神話から機能的リテラシーへ
6 生きるための文字:『イブラヒムおじさんとコーランの花たち』から
第二章 「文盲」という物語:二人の羊飼いの自伝から
1 放浪の羊飼いから宮廷付き学者へ:デュヴァルの物語
2 父の教えから作家たちの教えへ:ガヴィーノ・レッダの遍歴
3 「文盲」の読み書きと啓蒙思想
第II部 文字をめぐる思想
第三章 啓蒙の光の中で:神の書物から人間の書物へ
1 世界という書物:コメニウスの「小さな書物」をめぐって
2 ルソーとコンディヤック:二つの透明な文字
第四章 自然言語と文字:聾教育と手話の発見をめぐって
1 自然言語としての声と身振り
2 手話の発見と文字言語
第五章 公教育と文字の思想
1 フランス語作文の思想
2 「母語」と文字をめぐって
エピローグ
註
あとがき
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
30
文盲の羊飼いから知識人に成った二人の事例が面白い。文字は、地元のムラから普遍的な世界へのパスポートのようなもの、そして、時間を越えて知恵を受けとることを可能にし、社会に返すミッションをも与えてくれる。特に二人目のサルディーニャの人は宮本にも似て、二つの世界を意識的に往還する。◇コッポラの映画、現代の米仏の識字教育、手話の歴史(これも興味深い)と、文字を使えるようになることをめぐっての思考。文字は文字だけじゃない、その理解には、私の中に参照するべき文脈が必要になる。そちら側の重要性がかえって強く感じられる。2016/05/03
オオタコウイチロウ
0
“リテラシー”といってもさまざま。そういった多様性と、そこに関連した自由らしきものがあると、いいことを言ったらしいデリダ。第一章を読み、最終章も読もうと思っていたが、やめる。2024/08/08
-

- 和書
- 日本の企業と産業組織