内容説明
壬申の乱の勝者である天武天皇以降の日本は、律令に基づく専制君主国家とされる。だが貴族たち上級官僚とは異なり、下級官僚は職務に忠実とは言えず、勤勉でもなかった。朝廷の重要な儀式すら無断欠席し、日常の職務をしばしば放棄した。なぜ政府は寛大な措置に徹したのか。その背後にあった現実主義とは。飛鳥・奈良時代から平安時代にかけて、下級官僚たちの勤務実態を具体的に検証し、古代国家の知られざる実像に迫る。
-

- 電子書籍
- 月刊不動産流通 2025年 11月号
-
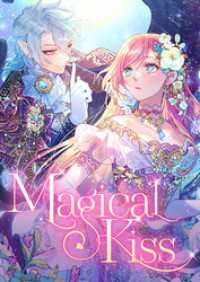
- 電子書籍
- Magical Kiss【タテヨミ】(…
-

- 電子書籍
- 西洋政治史
-

- 電子書籍
- アラビアの花嫁【分冊】 12巻 ハーレ…
-
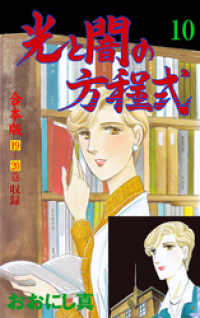
- 電子書籍
- 光と闇の方程式【合本版】 10 セレブ…



