内容説明
物理学者は研究だけでなく、日常生活でも独自の視点でものごとを考える。著者の「物理学的思考法」の矛先は、日々の身近な問題へと向けられた。通勤やスーパーマーケットでの最適ルート。ギョーザの適切な作り方、エスカレーターの安全性、調理可能な料理の数…。超ひも理論、素粒子論という物理学の最先端を研究する著者は、何を考えて学者になったのか? レゴを愛し、迷路づくりに勤しむ少年時代。数学の才能の無さに絶望し、物理学の面白さに開眼した大学時代。思考に集中すると他のことが目に入らず、奇人扱いされる研究者人生…。超ひも理論、素粒子論という物理学の最先端を研究する学者の発想は、日常をまさに異次元のものにしてしまう。面白く読み進めながら物理学の本質に迫る、スーパー科学エッセイ。
目次
はじめに
第1章 物理学者の頭の中
第2章 物理学者のつくり方
第3章 物理学者の変な生態
問診票
さらに思考法を深めたい方へ
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
165
京大理学科教授の科学エッセイ。大阪弁全開のボケ?と奥さんのツッコミ?で物理学者の(理論屋)頭の中やつくり方や変な生態がとてもユーモラスに書かれています。どれもおもしろいけれど、私が1番好きなエッセイは「たこ焼き半径の上限とカブトムシについて」…たこ焼きの本質とは表面固めで中はトロッとしていると定義し、それを昆虫の大きさに共通点を見出した。大きなカブトムシでも角を除いた体部分は半径2センチほど。昆虫は外骨格で体の全体重を支える構造であり、内部は様々な器官が収まりトロッとしている…一緒やないかぁーい!だって…2023/06/05
ehirano1
126
四六時中ほぼ学問のことに支配され(=敢えてそのように支配しているwww)、何でもかんでも式にぶち込んで数値化して比較したり、予測したりは理系の性なので仕方ありません。私はそんな性がむしろ好きです。周囲は迷惑を被ること多々ですが、「愛すべき偏屈」ということでご理解いただきたいと思っています。因みに、巻末でしょうかいされていた著者の著作の1つである「超ひも理論をパパに習ってみた」はタイトルだけでもう読みたくなりました。2025/02/25
rico
120
文系人間の私には呪文にしか見えない謎の式を駆使し、世界の秘密を解き明かすべく活躍されてる物理学者さん達は、この世をどう見ているのか。物体を球とみるとか、何でも計算するとか・・・「どーだ、面白いだろ!」て感じは少々うざいが、世界への真摯な眼差しや溢れ出る知の喜びには、こんな仕事したい!て思わせる力がある(無理!)。とはいえ、バーベキューでマッチを忘れどうやって火をつけるか30分も楽しく議論する方々に付き合いきれるかと言うと・・・(笑)。切符の数字を計算して10にするの、理系の人から教えてもらったなあ・・・。2021/07/24
trazom
120
「すごい思考法」などと大上段に振りかぶったタイトルの本は、大抵は見掛け倒しで失敗するものだが、この本はいい。橋本先生の洒脱な文章から、物理学者の「ものの考え方」が見事に浮かび上がっている。理学の特殊性、数学と物理の違い、理論物理と実験物理との違いなどが解きほぐされるが、理論物理学者の著者が、数学者や実験物理学者への敬意を失わない姿勢には、とても好感を覚える。日常生活の中の身近な題材を元にして、楽しくて考えさせられる、素晴らしい科学エッセイだと思う。オチに登場する奥様の一言も秀逸。2021/04/04
どんぐり
89
あらゆる現象を数字に置き換える習性から逃れられない物理学者の思考を1話4ページに記したエッセイ。駅の構内の壁に「1759」と書かれた落書きを見て、素数からその先に何か意味があるのではないかと考えてみたり、ある時は、手作りのギョーザを作るのに皮が足りなくなるのを防ぐために、「ギョーザの定理」を完成させたりする。経路積分、17種類の素粒子、ファインマン図など難しい話も出てくるけれど、ユーモアに満ちた文章が面白い。本書の効能として理系力に論理力の強化、理系ワードの習得がある。著者は阪大理学研究科の教授。2022/07/01
-
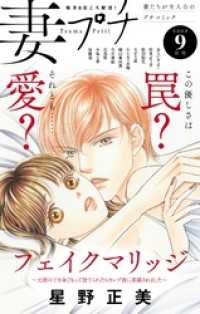
- 電子書籍
- 妻プチ 2023年9月号(2023年8…
-
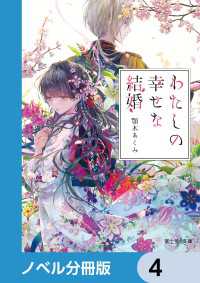
- 電子書籍
- わたしの幸せな結婚【ノベル分冊版】 4…
-

- 電子書籍
- 婚約破棄は蜜愛のはじまり~ワケあり公爵…
-
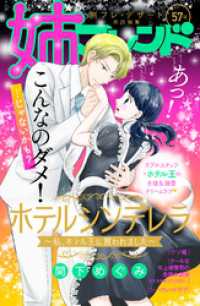
- 電子書籍
- 姉フレンド 57号
-
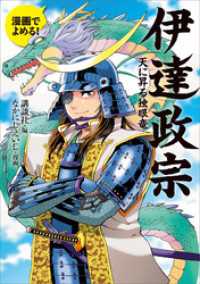
- 電子書籍
- 漫画でよめる! 伊達政宗 天に昇る独眼竜




