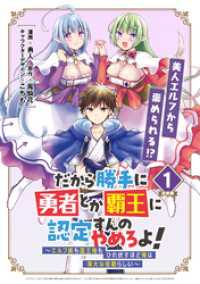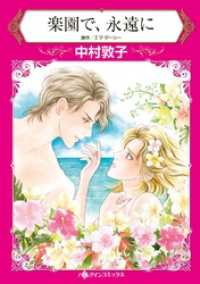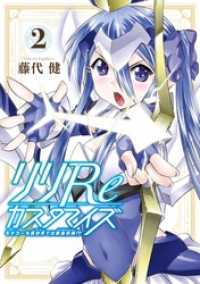内容説明
鎌倉時代の大仏師、運慶とはいかなる存在だったのか。
定朝を祖とする正系仏所三派中の奈良仏師に連なる運慶。
朝廷・幕府という二元的権力構造による時代の大きな変動期、
院・天皇・将軍・御家人など各種パトロン層の依頼を受けて
東大寺・興福寺の復興、円成寺・願成就院などの様々な造像に
関わった実情と、工房主宰者としての実力とは?
後に「霊験仏師」「天才」とも冠されることになる運慶の実像に迫る。
目次
第一章 造像と仏師
第二章 運慶論の形成と鎌倉時代彫刻史
第三章 「運慶作」の実情――仏像の制作と工房
第四章 背景としての社会構造と造像及び仏師――運慶はいかなる存在か
第五章 鎌倉新様式とは――「写実的」表現と本覚思想
第六章 運慶の事績上の問題点
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chang_ume
11
運慶「神話」の相対化を図る。仏像制作体制の再検討を踏まえ、般若寺大日如来像を「康慶」作とした新解釈は、興福寺北円堂仏像群を運慶作とした理解と整合するもので、「運慶」作が特権的に評価された現状に一石を投じるもの。また奥健夫氏の業績をもとに、鎌倉彫刻の過剰表現を中世「生身仏像」信仰ならではの表現として再評価し、本覚思想を鍵概念として仏像史の系譜に位置づける。ただ本書主旨でもある「写実」批判については、辞書的な語義解釈にとどまるようで、写実(理想主義)を扱うならば、西洋美術史の古典主義理解が不可欠ではと思った。2021/04/24
田中峰和
5
日本史で習う仏師と言えば、運慶くらいしか思い浮かばない。それほど有名な運慶であるが、その実態、そもそも仏師についてもあまり知らない。鎌倉時代初期に活動した運慶だが、円派、院派と呼ばれる京都仏師とは別派の奈良仏師であった。父とされる康慶に連なる運慶は、慶の一字を名乗ることから慶派とも呼ばれる。天才運慶論が確立したのは、明治以降の西洋美術の写実主義の導入と結びつく。運慶ものみを持っただろうが、むしろ寄木造を一般とする造仏は大仏師とその指示を受ける数人の小仏師、さらにのみをふるう数十人の弟子たちが参加する。2020/11/15
こまさん
1
「運慶神話」に対する斬りこみがメイン。たいへん勉強になった。2020/11/16
katashin86
0
現実の人体を表現した「写実的」スタイルに感じ取られる創造性から、日本仏像史の巨星として特別視される運慶。本書はその流派的立ち位置、表現の由来、運慶の事績が拡大し続ける現状への批判など、通説的見解を排し、仏師としての実像に迫る。 朝廷・公家・武家それぞれをクライアントにもつ有能な工房経営者であり、写実表現も自身のクリエイティブではなく当時の仏教思想を背景にするものとする著者説は納得できる。しかし、通説・重ねられたイメージが「ご由緒」としての意味・価値をもつ仏像を、フラットに拝することの難しさもまた感じた。2020/11/30