内容説明
歴史家・磯田道史氏がライフワークの1つとして研究を続けている日本の震災史を、体系的にビジュアルでまとめた本です。古文書に基づいて当時の人たちがどのように被災し、どのように復興を果たしたのかを伝えることで、写真や動画のない時代の災害を今に甦らせると同時に、今の私たちに役立つ教訓や防災対策につながるようにします。 ・地震、津波、噴火、台風、土砂崩れ、感染症、歴史的災害にまつわる古文書を、磯田道史が徹底解説!! ・災害の専門家、河田惠昭が災害のしくみ、避難方法を解説。 ・数十年以内に起こる確率が高いと言われている、「首都直下地震」「南海トラフ巨大地震」に備えることができる。 ・災害とともに生きてきた、日本人の復興の知恵を知ることができる。 「昔の災害はちょっとこわいけれども、見ておいた方がいい。私と一緒に『災害の日本史』の旅に出かけましょう。読んでおいたら命が助かるかもしれない、こんなマンガはそうはないですよ」磯田道史
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
98
私は漫画は一切読まない。しかし、河田惠昭先生(本書では防災監修)から是非読むように勧められてこの本を手にする。地震/津波/噴火/台風・水害/土砂災害/感染症/防災・減災・復興の7章にわたって、災害の歴史と防災の要点がまとめられたいい本だとは思う(でも、紙幅の半分を占めるマンガは要らない。説明文で十分)。改めて、日本の歴史は災害の記録だと実感する。災害を契機に権力を失った人もいれば、鍋島閑叟のように災害(シーボルト台風)の復興を通じて社会の変革を果たした人物もいる。災害(コロナも)は権力の本領を露わにする。2021/07/11
もんらっしぇ
72
なんだか最近地震多くないですか?(-_-;)先日読んだ『歴史とは靴である』が非常に良かった磯田先生。そもそも大学一年生の時出会った「浅間山噴火の歴史」の講義がきっかけで歴史学者になろうと思ったそうな。その後は回り道をしつつも例の3.11のライブ映像に愕然。また本腰を入れて災害の歴史の研究に打ち込んだとの由。本作は地震、津波、噴火、台風、土砂崩れ、感染症等々歴史的災害にまつわる古文書を先生がライフワークとして解読を続けてきたものをヴィジュアル的に分かりやすくまとめた一冊。過去に学んで未来に備えるべしですね♪2022/05/06
たいぱぱ
67
子供たちや若い世代に知ってもらう為、歴史学者・磯田さんの自著から地震、津波、噴火、台風、感染症等の事象をピックアップしマンガ化した1冊。マンガと侮ることなかれ、文章の方も読み応え十分です。数々の古文書に遺された災害の歴史を読むだけでも教訓になる。津波に襲われ幼子を波に放り投げ年老いた親を助ける。昔の儒学的思想はありえないけどこれもまた歴史の一部なんです。最短で90年周期の東南海地震はおそらく2030年代半ば。しかし自然は法則など越えてくる。仰る通り防災を生活に根ざした習慣、文化にして被害を少なくしたい。2021/04/22
shiho♪
35
先日、子どもと名古屋大学の減災館を訪れた際に、災害の歴史は大事と学んだので、詳しく知るのに適した本。読友さんからの紹介。テレビでもお馴染みの磯田先生の災害に対する熱心さが伝わる。 地震や土砂災害など繰り返す歴史から我々はある程度の対策や知識を得ています。津波が起きたらここへ逃げる…など。しかし「災害とは人知を超えるもの」。想定より大きな被害だったら、「とっさの判断」が生死を分けることにもなる。ここなら大丈夫だろう、という思い込み(正常性バイアス)が命取りに。普段からの心のシュミレーションも大切。2021/04/13
かおりん
34
古文書(こもんじょ)から災害史を読み解く。地震、津波、噴火、台風・水害、土砂災害、感染症のそれぞれの日本史・歴史が各章にまとめられている。平時には忘れがちな備えや防災を改めて考えさせられた。マンガもあり、分かりやすい解説で読みやすい。2021/06/20
-
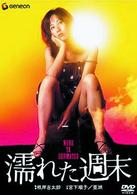
- DVD
- 濡れた週末







