内容説明
バリが失ったもの、守り続けているもの。この島は、何故かくも旅人のこころをからめとるのか!? 究極のバリ島読本。バリの迷宮をさまよう――目も醒めるような青い水田、耳に優しいガムランの音。小さな遺跡を訪ね、ウブドのアートや市場の喧騒に酔いしれる日々。バリは、何故かくも旅人の心をからめとるのか? 暮らし、食べ物、祭り、舞踊、言葉、暦……。バリ島の魅力に深くふれた名著『バリ島 不思議の王国を行く』に書き下ろしを加えた、究極のバリ島読本。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
makimakimasa
7
年末年始のバリ島旅行(4年振り)に合わせて。元は1986年(自分が生まれた年)に書かれた本に、1997年の再訪記を加えた構成。大規模観光地化する前の素朴な時代、年中お祭りに忙しいバリ人の伝統に彩られた日常と精神に触れる。一番多い名前は男も女もワヤンだそうで、自分の迎えの運転手もそうだった。バリ・ヒンドゥー総本山のベサキ寺院はいつか行きたい。ウブドがアートの中心地になったのは1927年にアトリエを構えたドイツ人画家シュピースの功績という。文体は微妙で、他の日本人や白人の観光客に時折見せる不遜な態度が残念。2023/01/06
80000木
5
著者のように、ワルンで手で食べるとか、デンパサールの安宿に泊まるとかは、ちょっとぼくの身体は受け付けなさそうやけど…熱気ムンムンのバリの空気を思い出して楽しかった。バリの駆け落ち婚の説明と、葬式の話はおもしろくて笑った。海岸の埋め立てを止めた政治家の話もカッコいい。政治家は民衆とのパイプ役、そういえばそやな、日本じゃ忘れがちかも。この本の出版から、さらに観光地化は進んでいるだろうけど、バリの神聖な空気と、人々の信仰心は、失われないでほしいと祈るばかりです。2017/05/19
saemo
3
僕がバリに最初に訪れたのは20年近く前で、その後に何度か訪れているためか著者のバリ観には懐かしさを憶えた。バリの風俗を知る上で参考になると思うが、この本を読んで感じたのは異文化を知るにはまず自分の文化を理解しなくてはいけないということ。そして、伝統が常に変化していくことがバリにダイナミズムをもたらしているのだろう。2009/07/13
ナウラガー_2012
0
プダンダ(高僧)は日々、規律を課した厳しい生活を送り、古文書の勉強はもちろん、ベモに乗ったり、ワルンで食べたり商店で買い物などしない。バリではお布施に現金を包む習慣がないため、経済的にも困窮する。ウパチャラ=宗教儀式一般を言う。お祓い/竹は奇跡の植物で、広島の原爆でも竹だけは生き残った。海抜千m以下で、気温が20度以上ならどこでも育つ2021/09/15
ナウラガー_2012
0
のは法律違反だとしたがリハをみた役人がすっかり気に入って即座に許可したという。レゴンの踊り子はかつては王宮のおかかえで、王の求めに応じて踊った。少女が大人になると妻に娶った。男はバリスを踊るが、戦場に赴く戦士の踊り。ケチャも本来は、レゴンの原型、サンヒャン(神様)・ドゥダリ(天使・妖精)の男声コーラスだった。これにラーマヤナの物語をアレンジしたものがケチャで考案したのはドイツ人の画家ウォルター・シュピースで友人の映画監督が「デーモンの島」というバリの映画を作るために頼まれて作った2021/09/15
-
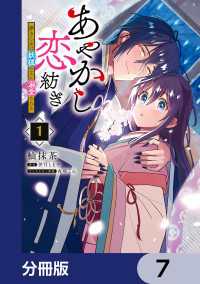
- 電子書籍
- あやかし恋紡ぎ 儚き乙女は妖狐の王に溺…
-
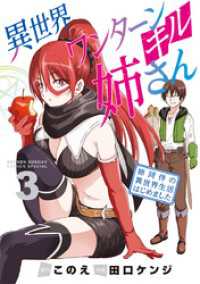
- 電子書籍
- 異世界ワンターンキル姉さん ~姉同伴の…







