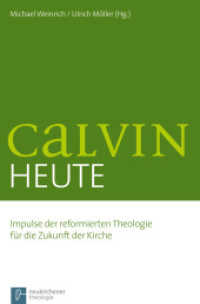内容説明
はるか縄文の昔から,日本にはさまざまな音楽が培われてきました.素朴な鈴や石の笛に始まり,仏教音楽の伝来,雅楽・能楽・歌舞伎・文楽の誕生と変化,文明開化による西洋音楽の導入,そして現代邦楽――.政治や宗教とも深く結びついた音楽の歴史をたどれば,日本の歴史の流れも見えてきます.コンパクトで濃厚な決定版!
目次
第一章 古代┴(一)音楽の定義┴(二)楽器の定義と縄文時代の楽器┴(三)弥生時代の楽器┴(四)倭国の対外関係と音楽┴(五)文字・儒教の導入と音楽┴(六)仏教の導入と音楽┴(七)音楽伝承の制度化┴(八)大仏建立と音楽┴(九)鐘の響き┴(一〇)東大寺の修二会┴(一一)音高についての古代の理論┴(一二)声明┴(一三)奈良から京都へ 平安時代の始まり┴(一四)平安時代の音楽のあり方┴(一五)雅楽の楽器と合奏┴(一六)雅楽での音高と時間の合わせ方┴(一七)中央と地方の文化的な交流と歌の役割┴第二章 中世┴(一)中世という時代┴(二)中世に共通する特徴┴(三)中世に盛んになった歌┴(四)日本最初の語り物 平家┴(五)日本最初の楽劇 能楽┴第三章 近世┴(一)近世という時代┴(二)琉球の音楽┴(三)アイヌ音楽┴(四)日本本土の音楽に共通する特徴┴(五)近世の楽器としての三味線┴(六)箏曲・胡弓・尺八┴(七)歌舞伎における囃子┴(八)七弦琴・一弦琴・二弦琴┴(九)近世での外国音楽への関心┴第四章 近代┴(一)明治時代の文明開化┴(二)教育における文明開化┴(三)神道の役割強化と音楽の利用┴(四)神道のための雅楽の重視┴(五)社会変革を乗り越えた能楽┴(六)解体された当道座と普化宗┴(七)文明開化のための西洋音楽の導入┴(八)近代の日本音楽の状況┴(九)近代における三曲界と文化触変┴(一〇)日本音楽の新しい記譜法┴(一一)近代末期の状況┴第五章 現代┴(一)敗戦国日本と音楽┴(二)民謡と民俗芸能┴(三)戦後の伝統音楽┴(四)伝統音楽における文化触変┴(五)音楽の活性化と公的組織┴(六)これからの日本音楽の状況┴あとがき┴事項キーワード┴人名キーワード┴曲名・旋律型キーワード
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サケ太
崩紫サロメ
はちめ
kao
pppともろー