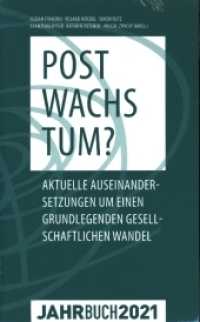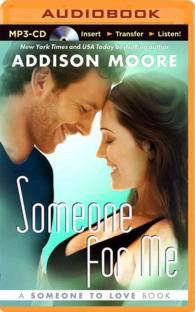内容説明
政党間の駆け引きに終始し,実質的な審議が行われない国会.審議空洞化の原因はどこにあり,どうすれば活性化できるのか.戦後初期からの歴史的経緯を検討した上で,イギリスやフランスとの国際比較を行い,課題を浮き彫りにする.「ねじれ国会」が常態化した今,二院制の意義を再考,そして改革の具体案を提示する.
目次
はじめに┴序章 政権交代は国会を変えたか┴第1章 戦後初期の国会運営 日本国憲法と国会法の枠組みの中で┴1 「国権の最高機関」としての出発┴2 本会議中心主義から委員会中心主義へ┴3 議員の待遇改善と補佐機構強化┴4 憲法施行直後の国会運営┴5 アメリカ・モデルの限界と修正┴第2章 空洞化する審議 五五年体制下の国会┴1 日本の立法過程の特殊性┴2 必要悪としての事前審査┴3 国会審議の空洞化┴4 小泉改革が果たせなかったもの┴第3章 立法府の改革構想 日本の議論、世界の潮流┴1 政府・与党関係のあり方┴2 世界の潮流 議会の自律性強化┴a イギリス┴b フランス┴3 「強い国会」と「強い内閣」の両立へ 何を変えるべきか┴第4章 二院制を考える 「ねじれ国会」を超えて┴1 本当は強い参議院┴2 二院制の意義は何か┴3 参議院をどうするか 独自性発揮への道┴終章 国会をどう変えていくのか┴1 改革の理念と方法┴2 改革の具体案┴a 国民に開かれた国会┴b 政府を監視する┴c 会期制度の見直し┴あとがき┴参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
19
日本の国会審議の形骸化について論じている。形骸化を招いた原因は、主として、自民党政権下で形成された与党事前審査の敢行がある。そして、党議拘束、国対政治、会期不継続原則、日程国会がある。欧州大陸諸国の標準的な立法過程では、内閣が自らの責任において内閣法案を起草し、与党議員は議会の審議過程でそれを精査し、必要な修正を加えていく。それでも決着しない場合は国会の審議に持ち越される。これに対し、(特に55年体制下の)国会では、内閣の決定を経ない草案段階の法案について与党の事前審査が行われ、その際に党議拘束を設ける。2017/08/01
zoe
16
2011年。国会は議論をする場では無くなってしまった。議決を伴わない自由討議はあってもいいのではないかと。その場で質問され、間違ったりするのが恥ずかしいのか、揚げ足をとってもジョークで受け流したり出来ず、少々けしからん間違いでも諫める程度で済まさず、追い込んで辞職させる勢いの寛容でない世の中がそうさせるのか。事前に質問を投げて、回答書をひたすら読む。結果だけ聞いてても面白くないし、前日の夜中や早朝まで調整しているから本番ではぐぅぐぅ寝ている場面が写される。本当のところ、議論の過程を見て聞くのが面白いし、→2025/03/09
浅香山三郎
15
日本国憲法下の議会のあり方といふそもそものところから始めて、外国の議会改革についても広く触れて、国会の改革案を提示する。弱い政権と弱い国会といふ性格づけをベースに見ていくと、審議拒否や強行採決が起こる構造も見へてくる。国会の調査権の強化や会期制の見直しなど、結論も妥当。2019/08/07
人間
9
なぜ国会(委員会審議)が茶番と化すのか。何点も複雑に絡み合った問題はあるが、法案提出者(議員にも提出権はあるがリソースの関係でほぼ内閣法案)の修正権に厳しい制限があること。委員会審議に先立ち与党内で事前審査が行われ、委員会審議が始まると党議拘束がかけられるため与党内からも反対することはできない。悪法案は野党は審議拒否などで廃案にするしか手がない。与野党が事前にすり合わせするのがいわゆる国対政治。茶番は何も与党が悪いor野党が悪いばかりではない。仕組みに問題があるように思う。2020/05/09
takizawa
9
国会審議を実りあるものにするためにはどのような改革が必要かという観点から書かれた国会入門書。巷でよく語られる国会批判(議員立法の少なさ・官僚主導等)の妥当性についても随所で検証されており社説をなんとなく読み流していると気付かない問題点がわかる(議院内閣制である以上内閣提出法案が多いのは当たり前。事前審査制が生まれたのは内閣の国会関与が制限されすぎていたことが原因等)。国会改革を語る際に必要な論点や前提知識が提示されているといえそう。2011/02/18