内容説明
▼「そんな病気はありません」
痛みや苦しみを患いながらも、医療者によって「疾患」を診断されず、
あるいは診断を受けても、他者から「病い」を認められない。
そんな「病い」を生きる人びとの生の困難と希望を描く。
本書では、「痙攣性発声障害」「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」「線維筋痛症」という3つの「論争中の病」を取り上げ、50名弱の患者への聞き取り調査などから、当事者が抱える深刻な困難や社会的経験の分析を行う。ここでいう「論争中の病」とは、生物医学的エビデンスを欠いているために、病気の実在性に疑義が呈され、患いの正統化をめぐって医療専門家と患者、医療専門家同士、あるいは患者をめぐる周囲の人びとや世論も加わって「論争」が生じている病を指す。
患いに名前を与えられず、名前を与えられるだけでは必ずしも苦しみを緩和されない「論争中の病」を患う人びとが、この社会で直面する困難や医療に対する希望を、私たちはどのように理解することができるのか。当事者へのインタビュー調査から、彼らが抱える困難や病名診断が当事者に与える影響を明らかにする。
目次
序 章 患い・診断・論争
第1章 「論争中の病」をめぐる問題
1 「病い」から「論争」へ――医療社会学のアポリア
2 医療社会学の分析視角
3 「論争中の病」とは何か
4 「論争中の病」をめぐる問題
5 おわりに
第2章 診断を社会学的に研究するということ
1 診断とは何か
2 医療社会学における診断の布置
3 診断の社会学に向けて
第3章 「病名がないより病名をもらえた方が嬉しい」
――「痙攣性発声障害」の当事者の困難と診断
1 はじめに
2 「痙攣性発声障害」を患うことの困難
3 「病気」の社会的実在性を担保するものとしての診断
4 患いの社会化と診断のポリティクス
第4章 「何もできることはないけど愚痴なら聞きに来ます」
――「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」の当事者の困難と診断
1 はじめに
2 「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」を患う人びとの病気行動
3 相手にされることのない患い
4 「活動的な患者」を引き受ける
第5章 「そんな病気はありません」
――「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」および「線維筋痛症」の当事者の困難と診断
1 はじめに
2 「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」および「線維筋痛症」の当事者における診断の効果
と限界
3 診断のパラドックス――周囲の人びとによる患い/苦しみの脱正統化
4 おわりに
第6章 「論争中の病」と診断
1 「論争中の病」の診断が当事者に及ぼす影響
2 正統化をめぐるポリティクス
3 希望をめぐるポリティクス
終 章 「論争」からシティズンシップへ
1 生物学的シティズンシップを記述する
2 想像的な希望と可能的な希望
3 生きるための/肉の政治
4 「非市民化」への抵抗
あとがき
初出一覧
註
参考文献
索 引
感想・レビュー
-
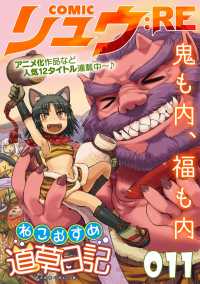
- 電子書籍
- COMICリュウ :RE 011








