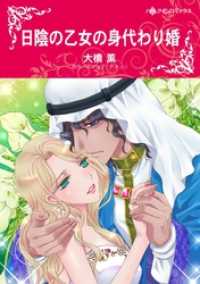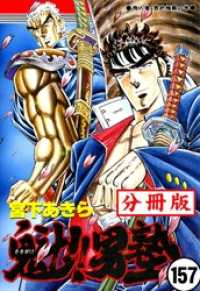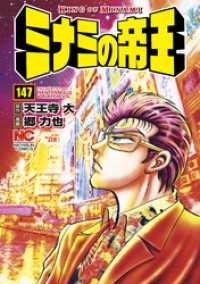内容説明
ひきこもり歴35年、「世界ひきこもり機構」(GHO)を創設した50代の著者が、インターネットを通じて世界のひきこもりたちやその支援者たちと対話した記録。フランス、アメリカ、インド、カメルーン、アルゼンチン、中国、フィリピンなど、世界13カ国に及ぶ国のひきこもりたちが普段何を考え、どのように暮らしているのかを明らかにした「ひきこもり」の常識を覆す衝撃的な本。
目次
はじめに
フランス ギードの場合
フランス テルリエンヌの場合
中国のひきこもり
アメリカ ショーン・Cの場合
アルゼンチン マルコ・アントニオの場合
インドのひきこもり
インド ニティンの場合
イタリア マルコ・クレパルディとの対話
父との最後の電話
パナマ共和国 ヨスーの場合
フランス アエルの場合
スウェーデンのひきこもり
バングラデシュ イッポの場合
フィリピン CJの場合
カメルーン アルメル・エトゥンディの場合
北朝鮮のひきこもり
フランス ジョセフィーヌの場合
台湾の映画監督 盧徳キンとの対話
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
65
地下茎とは言い得て妙。まさにひっそりと生命感に溢れた繋がり。もはや本人の主義や価値観の問題で、支援や治療は押し付け、おせっかいなのかとも思ってしまった。多くの海外ひきこもりに影響を与えたアニメ『NHKにようこそ』が俄然気になる。 2021/07/22
小鈴
32
ひきこもりは日本特有のもの、先進国特有のもの、資本主義社会の産物と分析されるが、欧米や発展途上国、福祉の発展した北欧や共産主義国の北朝鮮など各国のひきこもりの存在がそれらの視点を相対化してくれる。著者の言葉が刺さる。「人は皆、『自分の人生は意味のあるものであってほしい』と願うものではないでしょうか。そのため、多くの人は仕事に『すがる』のです。『自分は職場でこういう仕事をしている。だから自分の人生は意味があるものなのだ』と納得するために仕事をしています」→2021/02/23
たまきら
31
なんとまあ、壮大な世界の引きこもり達の紹介本です。著者の文章がすっきり説明上手で笑ったり一緒に胸を痛めたり。孤立しているようでも絶妙な距離感で関係を保っている彼らのコミュニケーションテクニックは、意外とコロナ期の今こそ実は学べるものが大きいのでは…と感じました。ひきこもり、がグローバルに使われ始める日も遠くなさそうだなあ…と思ってニュースサイトを検索したら、すでに結構国際的に認められているのね…。2021/08/05
akihiko810/アカウント移行中
26
世界中のひきこもり当事者たちにインタビューした本。印象度B 著者もひきこもり経験者(現在も?)で、かつて海外で「外こもり」してたりしてたらしい。語学に堪能らしく、世界中のひきこもり達の話をネットで集めているという。先進国だけでなく、バングラディシュ、フィリピン、カメルーンといった途上国のひきこもり事例もある。(この本がネットで紹介されたとき、北朝鮮の事例も紹介された気がしたが、本書に北朝鮮の事例はなかった。もしあったら当人はすごいシビアな環境だと思うが) ひきこもり当事者インタビューよりも、著者の意見2021/07/07
Speyside
22
35年来のひきこもりである著者が、世界ひきこもり機構というオンライン組織を立ち上げ繋がった、世界中の当事者へのインタビュー集。以前は「先進国特有の現象」「資本主義社会の産物」と専門家の間で考えられていたそうだが、中国やバングラディッシュの事例も登場し、世界中に普遍的な現象のよう。ひきこもった経緯や日々の思考など共感できる内容が散見され、自分が社会生活を営めているのは運が良かっただけという気がしてくる。「ひきこもりは生育歴等によって、仕事にすがることでは人生の意義を見いだせない人」という分析がとても示唆的。2022/03/29