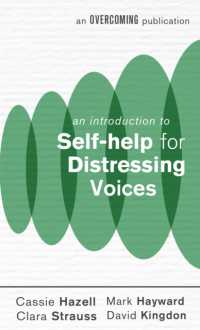内容説明
先進国の中でも,女性の社会進出が遅れている日本では,日頃から政策決定に女性の声が反映されにくい.そのため災害時の被災者支援も男性基準で進められ,女性被災者にしわ寄せがいきやすい.また被災地でのセクハラやDVなどの被害も表面化しにくい.東日本大震災の女性被災者たちの実状を報告し,多様な支援のあり方を考える.
目次
はじめに┴1 東日本大震災下の女性たち 何が起きたか┴第1章 見えない被害、届かない声┴第2章 災害時における女性への暴力┴第3章 雇用不安と女性┴2 多様な支援の形をもとめて┴第4章 「日本的支援」の歪みを問う┴第5章 支援の国際基準とは┴第6章 地域防災計画を見直す┴3 復興政策にも女性の声を┴第7章 女性を視野に入れた復興政策┴第8章 女性の意思を反映させるために┴おわりに┴【付録】女性の視点からの避難所づくりマニュアル┴コラム 1 被災地の女性の健康/2 災害とセクシャルマイノリティ/3 災害と女
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
9
共同生活としての避難所暮らしではコンセンサスが何より大切だと実感される内容。過剰にプライヴァシーを言うと、非常時なのだから止む無しと思えてくる。世帯主中心主義の弊害(29頁~)は、単身世帯激増にあって、時代に合わなくなっている。災害弔意金の話。先ほどの本では地名の国際基準が出ていたが、ここでは災害支援の国際基準がある(35頁~)。スフィア基準といった、ジェンダー・多様性への配慮があるという。脆弱な人々への配慮は大切。脆弱性の定義も刻々変化する被災地では変化するかと思う。感性や閑静が失われる災害に女性の眼。2013/05/30
M
1
東日本大震災を経て、防災に対する意識が変わってきたと思う。防災に女性の視点が加わることは欠かせないことなのだとこの本を読むと感じる。この本で言及されているが、「女性」をひとくくりにしないことが、住民の多様性に配慮することにつながることなのだと思う。2013/03/20