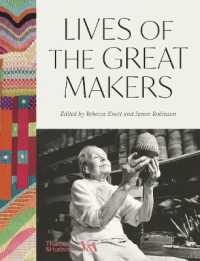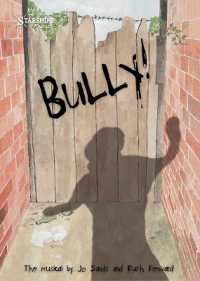内容説明
マスコミが信用できないなら,自分たちでメディアをつくろう! インターネット放送局Our Planet-TVを立ち上げ,独自の取材・発表を続ける著者が,激変するメディア状況の意味を読み解き,反貧困を訴える若者や,福島の子どもの健康を守るために立ち上がった親たちなど,多様な人々の情報発信の試みを報告する.
目次
はじめに メディアが激変する時代に┴第1章 ジャーナリズムが機能しないのはなぜ? 私の経験から┴第2章 今、誰もが発信者の時代へ┴第3章 世界に広がる「市民チャンネル」┴第4章 「小さな声」を伝えるために 始まる日本での試み┴おわりに 一人ひとりがメディアの主役に
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
25
コミュニティメディア:行政や企業から独立、市民独自の視点で情報を流すメディア(3頁)。ワンセグ:各局に割り当てられている13セグメントのうち、1SG利用(15頁)。ジャーナリズムの語源は日々書く日記。個人が情報の担い手となり、多様性確保を(19頁)。市民は消費者発想から抜けられず、既得権益の大資本が内輪で決める構造(44頁)。内閣支持率も信用できない。小さな声の事例:アイヌ、性的マイノリティ(52頁~)。2016/02/05
ののまる
8
薄い本だけど示唆に富む。主体性なくテレビを垂れ流して観ている人(家)というのが嫌いなのだけど、そういう人と同じ一票なんだよな〜と思うとゲンナリする時がある。2016/02/06
ハンギ
2
白石草(しらいし はじめ)さんがメディアへの政府の圧力を経験した事から、市民に開かれたメディアの必要性を痛感し、そして市民主体のメディアをつくって行く様子が描かれている。欧米ではメディアのコントロールは直接的に政府が握っているわけではなく、第三者による監視が行われているらしい。日本では占領期にそうした機構が作られたけど、吉田茂が解体したそうだ。いまでは放送事業は免許制になっており、突出した報道を行うと、政府や党から免許が取り上げられる事も考えられるという。自由に報道できないのはこうした理由もあった。2012/01/17
更紗蝦
1
薄くてすぐに読み終えられる本ですが、日本のメディアのあり方がいかに時代にそぐわないか、国民一人ひとりのメディアリテラシーがいかに低いかが、分かりやすく述べられています。「パブリックアクセス」という概念が、日本の中でほとんど周知されていない現状は、異様としかいいようがありません。2013/05/02
kenta
1
とっても薄い本ですが、内容が濃く良書だと思います。 ・「大きなメディア」に信用を失いつつある方 ・自分で「小さなメディア」を始めようとしている方 は是非、読んでみて下さい。 日本のメディアの現状と、世界のメディアの多様さに触れることが出来ます。 あぁ、ラジオとか動画編集やってみたいなぁ〜2012/09/15