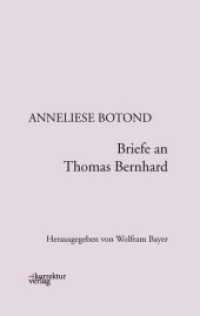内容説明
超高齢化が急速に進むわが国では、「終活」の名のもとに、多くの人が死への準備をしているように見えます。しかし、人間は死を“予行演習”することはできません。ソクラテスが「哲学とは死のレッスンである」と述べたように、哲学こそが最強の「終活」なのかもしれません。
本書では「哲学者」の枠にとらわれず、釈迦、ソクラテス、プラトン、キリスト、空海、源信から、キルケゴール、ニーチェ、フッサール、ハイデガー、ヴィトゲンシュタイン、サルトル、セーガン、手塚治虫まで、「死」について考え抜いた偉人たちを取り上げ、そんな先哲たちの死生観と、彼ら自身が一人の人間として「死」にどう立ち向かったかをたどります。また、先哲たちの著作だけでなく、アニメ、ゲーム、映画、ドラマなども引き合いに出し、現代の死とさまざまなブームにも目を配っています。
難解な哲学書、聖書、仏典などをわかりやすく読み解き、死をキーワードに、哲学とキリスト教、仏教などの本丸に乗り込みます。
著者・内藤理恵子氏は、葬送文化のフィールドワーク、ペットの葬儀などの研究にも携わり、さまざまなメディアに登場する気鋭の哲学者・宗教学者。また、似顔絵師として生計を立てていたという異色のキャリアを持ち、その腕は本書でも活かされています。
誰でも一度だけ経験する「死」。重くなりがちなテーマですが、どこか笑える哲人たちの生きざまも軽妙に描かれ、読んで楽しい哲学入門です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
33
「死」を切り口として哲学者たちを描く著者の語り口は面白い。キルケゴール、ヘーゲル、ショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガーなどにおいて「死」が重要なテーマであるのは言うまでもないが、私自身、ヴィトゲンシュタインやサルトルの中で、死の問題をそんなに深く考えていなかっただけに、新しい発見があった。ただ、ニーチェが多神教的な価値観の復活を目論んでいたとか、鈴木大拙がニーチェの宗教批判を換骨奪胎して平安仏教批判を行ったとか、手塚治虫がニーチェとサルトルの系譜に連なる哲学者などの記述は、余り納得がいかないのだが…。2019/11/05
テツ
17
大多数の人々はコロナウィルスが流行ってからはじめて自分や自分の周りの人間がいつ死ぬのかわからないという事実に気づく(そしてきっとすぐに忘れる) 生きるとはなんなのか。死とはなんなのか。決して逃れることのできない死というイベントを前にしてぼくはどう生きていくべきなのか。昨今の騒動は古今東西の哲学者たちが魂を費やして思考してきた死について考えるいい機会なのかもしれない。死はとても身近にありいつやってくるのか解らない。そんな残酷極まりないぼくたちの在り方を忘れずに日々を生きていかなければならない。2020/07/14
コージー
11
★☆☆☆☆2020/02/04
harhy
7
思想家たちが普遍的で本質的な問題を深く考え、全体として少しずつ前に進んできたのがわかる。2022/08/20
虎哲
7
2021年1冊目にして、2021年ベスト本か?「死についての博物誌」を目指したと著者が「はじめに」で語る通り、死について考え抜いた人を総称して「哲学者」と呼び、彼らの足跡や考え、当時の背景、我々の考え方をはじめ、時にサブカルチャーに至る後世への影響を親しみやすい文体で軽やかに論じる。「哲学者」として難解とされるハイデガーやヴィトゲンシュタインが出てくるため構えるが、哲学的素地がなくても理解出来る。イラストやたとえが読者の理解を助けるからだ。この本を読むまでほとんど知らなかったヤスパースの考え方に最も共感。2021/01/01