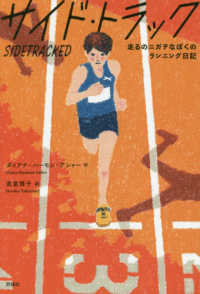- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
私たちは自分の人生の中で出会うさまざまな課題を、見つけ、調べて、解決することが求められる時代に生きている。日常の関心を一歩前に進め、「対話」を通じて学びを広げよう。生徒と教師に向けた「探究型の学習」のためのテキスト。
目次
第一章 「探究」とは何か
1 自分の人生の課題を解決する
「研究すること」と「生きていくこと」が分けられない社会
この本の目的
2 変わりつつある世界
現代社会最大の課題、環境保護
人工知能にはできないことが重視される社会
「何者か」ではなく「何を学んだか」が問われる
人との多様な関わりが求められる
世界はよい方向に向かっているが、努力を続ける必要がある
3 変わりつつある学び
一つの事柄をさまざまな視点から検討する力
4 探究する目的
複雑で多面的な存在である私たち
5 探究の授業の特徴
6 なぜ高校から始めたほうがいいのか
第二章 探究的な学びとは何か
1 文明と文化
2 探究の動機
3 日常の関心を一歩前へ進める
だれのため、何のための探究なのか
4 探究型の学習をどう進めるか──方針と流れ
仮説を立てることの重要性
実証を繰り返す
5 ポートフォリオ──学習過程の記録
第三章 探究型の授業と哲学対話
1 哲学対話によるテーマと問いの発見
「当たり前」を検討しなおしてみる
哲学はいくつもの教科や分野にかかわる問い
2 哲学対話のやり方
(1)準備と参加者
(2)対話の心構え
(3)共に考えること
コラム1 論理と推論
コラム2 隠れた前提
(4)対話の進め方
(5)対話における質問
(6)ファシリテータの役割
(7)メタ・ダイアローグのすすめ
第四章 文献収集と読み解き方
1 実証の方法
2 文献の探し方
(1)関連資料のリスト作り
(2)文献を手に入れる
(3)第二リストと文献メモを作る
3 文献の精読の仕方
4 要約の仕方
第五章 プレゼンテーションの仕方
1 プレゼンテーションとは何か
2 プレゼンテーションの仕方
資料
内容の構成
スライドの作り方と使い方
大切な質疑応答
発表の評価
3 ポスター発表
第六章 レポートの書き方
1 レポートとは何か
(1)問題に解答し、それを主張する
(2)理由と証拠によって主張を論証する
(3)論文の構成を守る
(4)形式と書式を守る
2 レポートの倫理
3 論文を相互に評価する
4 よいレポートとは何か
コラム3 論理的な文章を書くには
5 注と参考文献表の付け方
注とは何か、どのような場合につけるのか
出典注
引用の仕方
参考の仕方
参考文献表の作り方
あとがきと提案
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろくせい@やまもとかねよし
venturingbeyond
かんた
かんがく
武井 康則
-
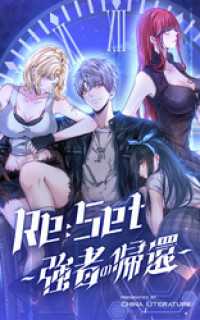
- 電子書籍
- Re:Set ~強者の帰還~【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 33歳独身女騎士隊長。第109~114…