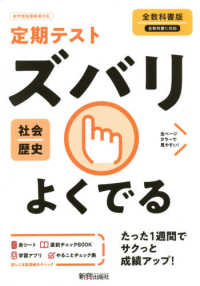- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
深海には、われわれの想像を超える生物が蠢いている。まったく光が届かない世界で、捕食者から逃れ、パートナーを見つけるために特化した視覚・聴覚・嗅覚、不思議な器官。海の男たちから「シーサーペント」とおそれられた巨大ウミヘビや日本の漁船が引きあげたニューネッシーの正体とは。文字通りメスと一体化してしまうビワアンコウのオス、スケスケ頭のデメニギス、生きた化石シーラカンス、ダイオウグソクムシの無個性という進化など、深海のモンスターたちの異様な姿と習性を、迫力の描きおろしイラストで紹介する。
目次
まえがき
第一章 怪物と呼ばれた深海生物
1 ダイオウイカ──〝巨大海ヘビ〟はマッコウクジラのディナー
怪物シーサーペント
ダイダロス・モンスター伝説
マッコウクジラの大好物
ダイオウイカのサイズ
ダイオウイカの生存戦略
「視力」対「聴力」
2 ラブカ──ヘビの顔をした深海ザメ
驚愕する魚類学者
古代ザメ「クラドセラケ」との同異点
サメの顎
歯の進化
3 ミツクリザメ──古代の巨大肉食魚の正統な後継者
生前の雄姿
学名命名の基準
古代ザメ「スカパノリンクス」の生態は?
4 ウバザメ、メガマウス、ニューネッシー──人は見たいものしか見えない
ニューネッシー熱狂の陰で
ニューネッシーのヴィジュアル分析
ニューネッシーの正体は一目瞭然
米海軍船にからまった巨大オタマジャクシ
気づかれなかった新種の巨大魚
魚竜に見間違えられたウバザメ
メガマウスの生態の謎
巨大な口の秘密
5 リュウグウノツカイ──古代から想像力を刺激する容姿
たてがみを持つヘビ
海の妖怪が消える理由
謎の生態のわかっていること
ちぎれた尻尾のゆくえ
6 レプトケファルス幼生──巨大ウナギ伝説の起源
このレプトケファルス幼生は誰の子?
幼生の意外な変態
巨大幼生の3タイプ
低栄養食に特化
アベコベの変態
第二章 想像を絶する深海の生態
7 ビワアンコウ──極端に小さいオスの役割
ビワアンコウに寄生する袋のようなもの
オスが小さいことの意義
8 デメニギス──透明な頭と巨大目玉の超能力
頭が透明の異形な姿
深海を泳ぐ映像で判明した事実
ギミックに満ちた魅力的な目玉
9 ダイオウグソクムシ──無個性という特殊能力
生物として汎用性が高いデザイン
進化も退化もまだない生活
生きたままのサメの内臓を食い荒らす
第三章 生きた化石は深海にいる
10 オウムガイ──貝がイカに進化する過程
貝とイカの共通点
世界中で知られる美しい貝殻
オウムガイの三日天下
オウムガイと魚、海の覇権争い
強敵ゴマモンガラ
運命の分岐点
オウムガイの謎
ネクトカリス騒動の悲しい裏話
11 コウモリダコ──独自のニッチで1億6600万年
地獄の吸血イカ伝説
低酸素環境下ののんびり生活
コウモリダコの食事
イカとタコの祖先
タコの系譜
コウモリダコが絶滅を免れた理由
12 シーラカンス──ダーウィン進化論の神髄
直訳すると空っぽのトゲ太郎
世界中でぞくぞく発見
進化の原則は自然選択
利用される間違い進化論
政治と科学
姿を変えない生物が進化理論の証拠
生存競争と自然淘汰とは
進化系シーラカンスの末路
生物淘汰の基準
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
きみたけ
ホークス
鷺@みんさー
Tomomi Yazaki