内容説明
「敦煌」は戦前・戦後を通じて、日本人の「中国への憧れ」を象徴する言葉であった。その最後の輝きとも言える1980年代、井上靖の小説『敦煌』『楼蘭』がロングセラーになり、「敦煌」は世紀の大作として映画化。NHK特集「シルクロード」が高視聴率を記録し、喜多郎のテーマ音楽がヒットチャートを駆けあがった。平山郁夫の描く西域の風景画はカレンダー等の定番でもあった。中国の改革開放政策の進展にともなって巻き起こったあのブームは、いつ、なぜ、どのように消えたのだろうか。
今や「シルクロード」という言葉は中国の経済圏構想「一帯一路」に付随するものになってしまった。中国が世界の脅威と見なされる現状で、日本が隣国とどのような関係を構築すべきかを考える必要に迫られている。20世紀の日本人が何を背景に、どのような中国イメージを形成してきたのかを知ることは、その大きな手がかりとなるだろう。
目次
第一章 井上靖と「敦煌」
第二章 日中国交正常化とNHK「シルクロード」
第三章 改革開放と映画『敦煌』
第四章 平山郁夫の敦煌
第五章 大国化する中国とシルクロード
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
98
「敦煌」と聞いてすぐに何かのイメージが思い浮かぶ人は、日中関係の幸せな時代を知る人だ。―この冒頭の文に大きく頷いてしまう。「敦煌」に焦点を当て日中関係の変遷を、作家井上靖や平山郁夫画伯らの働きを追い読み解いていく。文革を収束させ改革開放へ大きく舵を切った中国。ちょうどその頃、80年代初頭に放映されたNHKのドキュメンタリー番組「シルクロード」に多くの日本人が魅了された。戦後、長らく閉ざされていた中国の扉が開き、西域やシルクロードなど未知の領域への憧れと社会主義中国への興味が重なり多くの人々の関心を集めた。2021/03/25
パトラッシュ
63
アメリカが映画や高い生活文化で世界にPRしたように、中国はシルクロードというレンズを通じて自国を見せようとした。NHKの番組に井上靖の小説と映画、平山郁夫の絵画など文化の力で日中友好を推進し日本の対中警戒感を抑えようとの意図があった。この外交的思惑は大成功し、多くの日本人が中国の歴史や旅情に憧れた。しかし中国が大国意識にとらわれ、共産党が本来の独裁体質をあらわにすると一切は雲散霧消した。ウイグル人が血まみれの弾圧を受けていると誰もが知る今、美しい敦煌の壁画は政治の暗い洞窟に再び閉じ込められてしまったのだ。2021/07/16
さとうしん
21
敦煌文書の発見から「監獄」化した現在の新疆ウイグル自治区の状況まで、敦煌を含めた日本人の「自分探し」としてのシルクロード観を総ざらいした本、なのだが、それにとどまらず堺正章の『西遊記』や徳間書店の「中国の思想」シリーズなど、80年代頃の中国理解、中国体験や日中関係にも話題を広げている。往時の熱気が感じられる筆致。2021/03/15
ジャズクラ本
16
◎井上靖「敦煌」、NHK番組「シルクロード」、平山郁夫のシルクロード作品の数々を辿り返しながら1950年代頃からの日中関係を掘り起こしている。上記3つの作品を知る世代とそれ以降の世代には対中意識として大きな温度差があると著者は言う。確かに1970〜1980年代には大きなシルクロードブームのうねりがあり、今から考えるととても儚い日中の蜜月期だったように思える。当時ウイグルの人々に見られた笑顔が現在は消え失せてしまっているという事実に行き場のない怒りを感じてしまう。コメント欄はウイグル関連とその他の備忘録。2021/12/19
Toska
12
今では想像することすら難しい、日本人が中国に憧れの目を向けていた時代。一世を風靡したシルクロード・ブームとは、戦前から連綿と続く西域への憧憬に加え、政治や経済、文化などの要請が上手く嵌り合った、それこそ奇跡のような現象だった。NHK「シルクロード」の取材が鄧小平への直訴で実現したというのは驚き。日中関係がそんな熱を帯びていた瞬間もあったのだ。1968年生まれの著者は身をもってこのブームを味わった世代で、自身や家族の体験談がいいスパイスになっている。2022/09/18
-
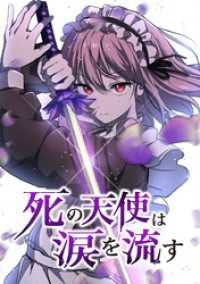
- 電子書籍
- 死の天使は涙を流す【タテヨミ】 EP.…
-

- 電子書籍
- 学園騎士のレベルアップ!レベル1000…
-

- 電子書籍
- 暮らし上手特別編集 つくり置きBOOK
-

- 電子書籍
- 燃ゆる星 新訳・与謝野晶子 プチキス(…
-
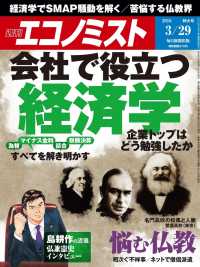
- 電子書籍
- 週刊エコノミスト2016年3/29号




