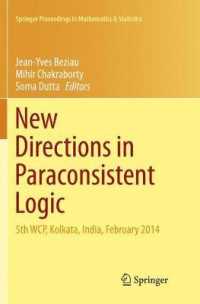内容説明
かつて女性中心で行われてきた家族の介護。今では男性(夫や息子など)が担い手の3分の1を占めるが、問題は少なくない。孤立し、追い詰められた男性介護者による虐待、心中などの事件は後を絶たない。他方で介護離職を余儀なくされる人もいる。本書は、悲喜こもごものケアの実態、介護する男性が集い、支え合う各地のコミュニティの活動を、豊富なエピソードを交えて紹介。仕事と介護が両立できる社会に向けた提言を行う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サケ太
19
非常に考えさせられる。介護、というのは今後多くの人間が関わらざるおえないものだと思う。私の仕事はそれに関係するわけだが、患者さんが自宅でどのような生活をしているか、具体的な状況はわかっていない事は多い。勿論、その生活に関わるご家族と直接話す機会もない。女性の仕事とされていた介護。それは、いつからか、何故なのか。江戸時代の事例を出して、男性が介護を行っていたというのは興味深かった。今後の課題は多い。介護に携わる男性の特性もあり、なかなか苦しいものもある。話し合う場、というのはどんな人にも大事だと感じた。2021/02/25
かんがく
12
周りに男性介護者が多いので「介護者=嫁」というジェンダー感覚は自分の中にはなかったが、現在介護の主な担い手となっている高齢者層ではそのようなジェンダー規範が強いことが様々な実例からわかった。「男らしさ」へのこだわりから、家事や買い物を行えない、介護の辛さを共有できないなど、介護のみではなく日本社会全体の持つ問題がよくわかった。2021/12/21
てくてく
6
団塊の世代あたりの男性は家事ができないことが自慢みたいなところがあって、そういう男性が親や妻の介護を行うとなると介護以前の家事でつまずいてしまうという点は想像しやすい。介護をするのが当たり前とどこか思われがちな女性と異なる男性が、今後介護を担当することが増えることは必至なので、介護以前の段階で、家事やSOSを発信することができるようになっていることが望ましい。男性が男性に向けて書いたという点で意義がある一冊。2021/05/22
ちくわ
6
「男性」による介護の「生の声」が数多く拾われている本書。著者は、介護のためのネットワーク作りを実際に担ってきた方である。本書のタイトルだけ見ると、ジェンダー規範との関係で、賛否のある捉え方が出てくるかもしれない。しかし、本書を読んでみると、男性による介護「のみ」を視野に入れているわけではなく、その切り口に始まり、「介護自体の社会化」を試みようとしている著者の意図がよくわかる。介護の担い手の属性はこれまで変わってきたし、これからも変わっていくと思う。自分が直面する可能性のある課題として、考えていきたい。2021/04/10
sk
4
男性介護者の実態について。これも社会問題だったのか。2022/01/14