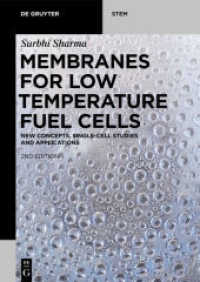- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「ナッジ」で知られるハーバード大学の教授がホワイトハウスへ。情報規制問題局の局長として、規制に関する法律の実際の立法に関わる。政策採用の是非の基準や、その際の費用便益分析の用い方まで、その内実を明らかにする。
目次
はじめに――フランクリンの代数
第1章 政府の中
第2章 人間的な帰結、あるいは現実世界の費用便益分析
第3章 尊厳、金融崩壊など定量化不能なもの
第4章 人命の価値その1――問題
第5章 人命の価値その2――解決策
第6章 リスクの道徳性
第7章 人々の恐怖
おわりに――規制国家を人間化する4つの方法
謝辞
訳者あとがき
補遺A――大統領命令 13563、二〇一一年一月一八日
補遺B
補遺C
補遺D
補遺E
注
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
27
前著の「シンプルな政府」をより専門家向けに著したもの。一般人には前著で充分ですね。斜め読みでした。キャス・サンスティーンの著書は最近日本で立て続けに出版されてますが、みんなこんな感じの二番煎じなのかなぁ‥‥。2018/02/18
さきん
25
規制制度を定める際の手段として費用便益という、事象を数値化して比較する手法を取る。人命も数値化されるが、所得、病気の種類、確率等によって、さらに数字の幅も広がりを持つために、省庁間から情報を集めて議論する機関がホワイトハウスに独自に存在する。命を数値化するなんてという道義的な批判もあるが、数字をそこまで絞り込まないこと(絞り込めないこと)、参考にするためであって、大きな要因を持つことは実際少ないと理解を求めている。専門色が強くて、自分が読むより、日本の官僚が読んだ方が良い内容。2018/12/31
スダタロー
2
著者キャス・サンスティーンのOIRA(情報・規制問題室。日本でいう内閣府規制改革推進室みたいな)時代の経験を踏まえた、行政による規制に対する定量的な効果測定の事例集的一冊。規制は予防的効果を期待して設定されている訳ですし、仮に当該規制がなかったとして懸念される事態が発生した場合の損失コストは示せるとしてもそれはその事態を原状回復するためのコストであって、類似の事態が何件発生し得るとかそういうことは分からないのである程度の推量が働かざるを得ないですよね。2021/05/04
jackbdc
2
タイトルの答として、費用便益分析の上では900万$と聞いて過大では?と感じた。10万人に1人の確率として1人90$分をリスク負担するという話を聞くとなんとなく納得できる気もする。判断はつかないが、透明性あるプロセスで専門性をもって判断していると理解できれば納得性を高められるのだろう。印象に残った点3つ、1.政府特有の難しさ:政府と企業の意思決定は相当な違いがある。政府の意思決定は相当に複雑。2.ハイエクとセン:相反する価値を体現する巨人の引用は分かりやすく表現としても面白い。3.訳者あとがき:秀逸。2021/03/07
tenorsox
1
政策決定等の際に人命をどの様に金額換算するか、まあ平たく言ってしまえば「政策の実行に必要なコスト<救われるであろう命の数x単価」の単価をどう算出するか)、について。 面白そうだと思って読み始めたが、ちょっと何言ってるか分からなかったので諦めてamazonの長めのレビュー見て終わらせることにした。2020/07/15