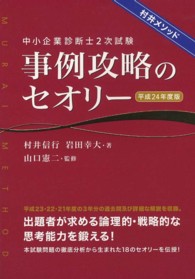内容説明
著者のこれまでの論稿をとりまとめた論集にとどまらない。憲法、教育法の学界に多大な貢献をされた著者の足跡を辿って時系列にその時々の研究と社会活動についての論稿を配置し、著者の学風、思想を提示する自分史的な色彩をももつものである。学術的価値の高い研究書であるとともに、その時々の著者をとりまく貴重な記録でもある。
目次
本書の序
第一部 研究と実践の軌跡――教壇生活中
第一章 憲法の議会制論から人権研究へ
日本国憲法を学ぶ――大塚雅彦先生の授業で
研究者生活への出発――有倉遼吉先生に師事
参議院の緊急集会制度の研究(修士論文)
請願権の研究
被疑者補償などの人権問題――内野正幸君からの示唆
第二章 教科書裁判などの護憲運動へ
憲法理論研究会の創設――鈴木安藏先生との出会い
教育問題への関心――宗像誠也先生との出逢い
国民の教育権か、国家の教育権か――教科書裁判の支援運動
個人の人権としての「学問の自由」
内申書裁判を支援
補章一 憲法理論研究会の創設の目的――社会科学としての憲法学の探求
補章二 教育要求権の論理――批判に答えて
第三章 教育権に関する裁判と判決――教科書裁判と学テ裁判
杉本判決の評価
高津判決と鈴木判決への疑問
第一次教科書裁判の終焉
学テ事件への最高裁判決――その分析
第四章 主権者教育権の理論
学校事故に関する研究活動
肢体不自由児の教育人権と福祉
主権者教育権を考える――護憲運動の中で
『資料・日本国憲法』と『日本国憲法なのだ』
第五章 学校の自治と社会教育の自由――教師の法的地位や図書館論など
学校の憲法教育
教師の法的地位――学校教育法第28条は
学習指導要領の法的拘束性
学校の自治と校内規則――イギリスや沖縄で学ぶ
社会教育の自由――図書館論を中心に
東京都社会教育委員などの体験
『解説教育六法』・『三省堂新六法』の編集
第六章 大学における学生の学習権――高等教育に関する研究の視座
私学助成の法理――国庫負担というべき
義務教育の無償――奥平・永井論争
第七章 子どもの人権を考える――教育法学の現代的課題
子どもは法学研究の対象の枠外か――日本法社会学会での体験
「子どもの権利をめぐる裁判」の研究――法政大学現代法研究所の研究プロジェクト
『教育条約集』の出版――国際教育法研究会の功績
子どもの人権連での活動――沼田稲次郎先生に共鳴
子どもの権利条約の普及と批准推進の運動
国会の参考人――菅直人氏らの協力
国会における条約の審議権――戸波江二君からの問題指摘
「子ども」か「児童」か――超党派女性議員が賛成・肥田美代子氏の活躍
第八章 日本教育法学会の発展
日本教育法学会の創設と発展・学会発展のための諸活動――マスコミへの対応、全国に支部結成など
設立の頃のマスコミ対策
支部結成
広報活動
大学の講座など・学会内における活動など――学会役員として
研究特別委員会などで
学会報告・出版・広報活動
第九章 日本公法学会の回顧
伝統的解釈法学批判――鵜飼信成先生に叱られた
憲法における「公」と「私」――残念な記憶
私稿『日本国憲法と戦後教育』――北京大学「国外法学」に翻訳掲載
巨人ファンの妙――芦部信喜先生の思い出
日本スポーツ法学会へ――新しい「スポーツ権」の提唱
さらに日本スポーツ学会(スポーツ・ネットワーク)の創設へ
補章三 スポーツ文化の潮流
第十章 研究と教育のフィナーレ――法政大学における23年
学外での飛び歩き
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann