内容説明
マクルーハンの「これまでの人類史とは、主導的メディアが形作ってきたメディア生態系、メディア・パラダイムの変遷の歴史であった」とする〈メディア〉史観の下、Google、ビッグデータ、SNS、ロボット、AI、ウェアラブル、情報倫理といった具体的で個別的な現象を分析の俎上に載せ、不可視のメディア生態系を暴きだす〈哲学〉。
目次
はじめに
序章 マスメディアの終焉と〈メディア〉史観
0―1 マスメディアの自壊から終焉まで
0―2 マクルーハン理論の本質と限界
0―3 「情報社会」における「知識」と〈学〉
第一章 グーグルによる「汎知」の企図と哲学の終焉
1―1 「グーグル」という問題
1―2 「汎知」の思想史
1―3 電脳汎知
1―4 ハイデッガーの“予言”
第二章 ビッグデータの社会哲学的位相
2―1 ビッグデータへの視角
2―2 ビッグデータの「3V」
2―3 ビッグデータとは“ゴミ”である
2―4 知識・情報・データ
2―5 「社会のデータ化」の思想史
2―6 液状化する社会と「データ」の覇権
2―7 データのオートポイエーシスと「配備=集立」の全面化
第三章 SNSによるコミュニケーションの変容と社会システム論
3―1 SNSという新たな〈コミュニケーション〉の登場
3―2 ルーマンの社会システム論と四つの疑問
3―3 世界社会と情報社会
第四章 人工知能とロボットの新次元
4―1 AIとロボットの現況
4―2 人工知能の展開過程
4―3 ロボットの展開過程
4―4 AI・ロボット・人間
終章 情報社会において〈倫理〉は可能か?
5―1 情報倫理とは何か?
5―2 倫理/道徳の本質とその史的展開
5―3 〈メディア〉の展相の中の倫理
5―4 情報社会における“普遍的”倫理の試み
5―5 三つの倫理的多元主義
5―6 システムと倫理
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
hitotoseno
Mc6ρ助
au-lab
たろーたん
-
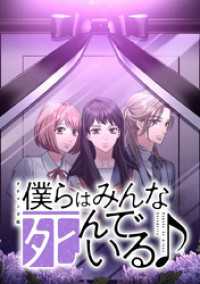
- 電子書籍
- 僕らはみんな死んでいる♪ タテマンガ版…
-

- 電子書籍
- 夫婦以上、恋人未満。【分冊版】 14 …
-

- 電子書籍
- 明日からは清楚さん~記憶喪失のフリして…
-
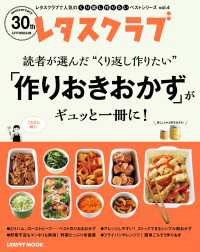
- 電子書籍
- レタスクラブで人気のくり返し作りたいベ…
-

- 電子書籍
- 死者だけが血を流す




