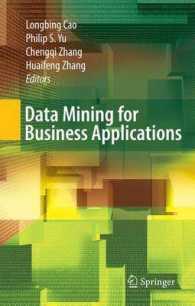内容説明
社会構築主義のブームを越え、改めて社会学の経験的探究の方途としての構築主義的アプローチを見直しヴァージョンアップを図る。個別具体的な事象がどのようにして構築されるのか、あるいはされてきたのか、その状況的もしくは歴史的な過程を観察し記述し分析するのに構築主義はどれだけ役立つのかを再検討するチャレンジングな試み。
目次
序章 構築主義で何をするのか――経験的探究の方途の成熟のために[中河伸俊]
1 方法としての構築主義
2 本書の構成
3 社会学のために
第I部 経験的なフィールドワークにもとづく構築主義
第1章 「ひきこもり」社会問題化における精神医学――暴力・犯罪と「リスクの推論」[工藤宏司]
1 問題の所在
2 「ひきこもり」社会問題化――「犯罪リスク」としての位置づけ
3 対応ガイドラインにおける「ひきこもり」
4 おわりに
第2章 「安全・安心」というるつぼ─生活安全条例を中心に[山本 功]
1 社会学と分類
2 「安全・安心」という価値のカテゴリー
3 「安全・安心」の出現
4 生活安全条例の制定
5 「安全」と結びつく「快適」――千代田区条例の場合
6 「安全」と結びつく諸カテゴリー
7 無限集合としての「安全・安心」
第3章 社会問題のサイクルと経路依存性――「非実在青少年」規制をめぐって[赤川学]
1 社会問題のサイクル
2 有害コミック問題から「非実在青少年」規制問題へ
3 自然史モデルからみる問題構築のプロセス
4 政策形成が全体を主導する――自然史モデルの修正
5 争点化されない問題
6 論拠の共有
7 論点絞込みのパラドクス
8 社会問題の経路依存性
第4章 緩慢な自殺から緩慢な殺人へ――日本における喫煙問題と受動喫煙という概念[苫米地伸]
1 『タバコの社会学』以後
2 日本における受動喫煙という概念の受容
3 嫌煙権運動のレトリック
4 結びにかえて
第5章 ケースを記録する――強調する,省略する,共有する[木下衆・緑山清]
1 はじめに
2 施設Xで働く
3 「何を書いたら良いのか,わからない」――記録第1期
4 既存の書式を用いる──記録第2期
5 「ハイライトすべきこと」の整理――記録第3期
6 おわりに
第II部 歴史を対象とする構築主義
第6章 男の猥談に現れる女の性欲 ――1960年代雑誌記事の「レスビアン」言説[杉浦郁子]
1 女性の性的主体化の可能性を問う
2 データ
3 「レスビアン」という主題/概念の普及
4 女性のセクシュアリティ管理への抵抗という課題へ
第7章 近代日本における被害者像の転換[佐藤雅浩]
1 なぜ「被害者」の歴史か
2 「被害者」関連記事の増減と記事カテゴリーの変化
3 近代日本における被害者像の変容
4 まとめ――加害と被害をめぐる00年代の言説空間
第8章 戦後日本の団地論にみる「個人主義」と「家族中心主義」――「孤立」をめぐる言説史の視点から[梅田直美]
1 「孤立」問題の再考にむけて
2 団地族の調査研究
3 戦後日本の団地論にみる「個人主義」と「家族中心主義」
4 おわりに
第9章 写真と写真ディスコース――コンポラ写真をめぐるカテゴリーの変遷[佐藤哲彦]
1 はじめに――本章の概要
2 写真と写真ディスコース
3 コンポラ写真とは何か
4 コンポラ写真とカテゴリーの遷移
5 結び─写真とカテゴリー
第10章 種の曖昧な縁――ハッキングの歴史的存在論について[石井幸夫]
1 序
2 何が構築されるのか?
3 記述の論理
4 私たち自身の歴史的存在論
5 種の曖昧な縁
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
ひろとん
ぷほは