- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
【コロナ時代。他者と共に生きる術とは?】コロナ禍によって世界が危機に直面するなか、いかに他者と関わるのかが問題になっている。そこで浮上するのが「利他」というキーワードだ。他者のために生きるという側面なしに、この危機は解決しないからだ。しかし道徳的な基準で自己犠牲を強い、合理的・設計的に他者に介入していくことが、果たしてよりよい社会の契機になるのか。この問題に日本の論壇を牽引する執筆陣が根源的に迫る。まさに時代が求める論考集。
目次
はじめに――コロナと利他 伊藤亜紗
第一章 「うつわ」的利他――ケアの現場から 伊藤亜紗
第二章 利他はどこからやってくるのか 中島岳志
第三章 美と奉仕と利他 若松英輔
第四章 中動態から考える利他――責任と帰責性 國分功一郎
第五章 作家、作品に先行する、小説の歴史 磯崎憲一郎
おわりに――利他が宿る構造 中島岳志
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろくせい@やまもとかねよし
242
2020年発足した東工大の未来の人類センター。そこの利他プロジェクトに参加する5名の大学教員が論考する「利他」。議論で用いるテーマは五者五様。伊藤亜沙さんの功利で定義する合理主義的利他。中島岳志さんの贈与からはじめ互酬性で考える利他。若松英輔さんの最澄と空海が発した利他の考察。國分功一郎さんの受動態の一つ中動態に含まれる利他。磯﨑憲一郎さんの小説創作のひらめきで見る利他。違う専門だからか、発散的印象。そもそも利他は利己から捉えるものだろうか。自己から他があるのか。もしくは他のなかに自己があるだろうか。2021/04/25
trazom
166
タイトルから倫理や宗教を想像したが、本書の視座は余りにも広範で深い。何より研究メンバー(=本書の五名の執筆者)が凄い。「利他主義は利己主義にとっての合理的な戦略」「利他の原理を共感にしてはいけない」「利他は他者を支配する」等の西洋的な問題提起に対して、利他行為後の「変に淋しい、嫌な気持」や、柳宗悦さんの自他不二の思想に思いを馳せる中島岳志さんや若松英輔さんの考察が心に残る。人は根源的に利己的であるとするか、「生物学の世界で、種の保存のために利他は当たり前」(大隅良典先生)と考えるかの立脚点の違いも大きい。2021/06/04
けんとまん1007
156
利他。以前は、あまり意識する言葉ではなかった。数年前、知人から、「利他の精神に溢れていますね・・・」と、言っていただいてから、頭の中にある言葉になった。中で、取り上げられているインドの例のように思う。自分自身では、何かを意識して行動しているわけではないのだが、そう評価された。伊藤亜紗さんのパートが、わかりやすく、自分の思いに近い。測りすぎや、ブルジットジョブも読んでいたので、そう思う度合いが強いのかもしれない。これから、重要なキーワードになってほしい。2021/07/04
おたま
138
「利他」を巡って、美学者、政治学者、随筆家、哲学者、小説家の五者が、それぞれの領域から論考を書いている。「利他」というものが、どのように生成してくるのかを書いているけれど、それぞれの方の掘り下げがもっと読みたいところ。それぞれで一冊の本が書けてしまうぐらいの濃い内容だ。概観として言えるのは、「利他」は自発的に為そうとしてしまうと、どこかで「利己」に転化してしまう。どうもそれは「起きてしまう」とか「もたらされる」ものではないか。そうした意味で「おわりに」で中島岳志の述べる「うつわになること」が当を得ている。2021/12/27
ハイランド
127
利他という最近流行りのキーワードだが、単純に利己の反対語という括りでは説明できない奥深さを持つワードである。伊藤氏中島氏の論考から考えさせられることは多い。感謝や見返りを期待する利他の行為は、変質した利己であり、利他というものが社会に組み込まれ、無意識に利他の行為を成しているような社会を目指すべきなのか。アドラー哲学にも通じるところがある。効果的利他主義や、慈悲に隠された優越感も興味深い。それにしても、理工系のカレッジである東京工業大学に「未来の人類研究センター」なるものが存在するのもなかなか興味深い。2022/06/10
-
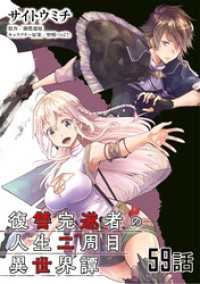
- 電子書籍
- 復讐完遂者の人生二周目異世界譚 第59…
-
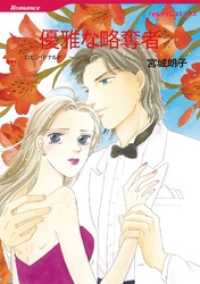
- 電子書籍
- 優雅な略奪者【分冊】 2巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- Berry's Fantasy 転生し…
-
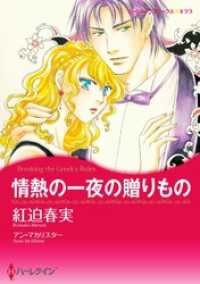
- 電子書籍
- 情熱の一夜の贈りもの【分冊】 11巻 …
-
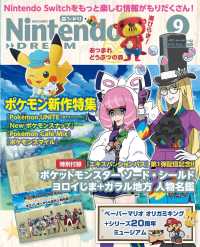
- 電子書籍
- Nintendo DREAM 2020…




