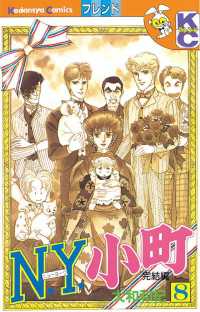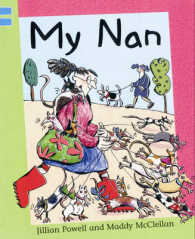内容説明
【カラー口絵16ページ付き】~受け継がれていく棋士の想い~
将棋界は歌舞伎や落語のように、師匠と弟子で技術が受け継がれていく面があります。
しかし、その師弟関係はさまざまで、そこには十人十色のドラマがありました。
本書は将棋世界に連載し、プロ棋士の深い絆を取材して著した「師弟」の連載を書籍化したものです。
著者はプロのカメラマンでもあり、「師弟―棋士たち 魂の伝承」(光文社)で将棋ファンの心をわしづかみにしたといっても過言ではない野澤亘伸氏。
できうる限りの徹底取材を重ね、それまで語られることのなかった逸話を棋士の口から引き出しています。
また書籍化するにあたっては将棋世界に未掲載の話や、少し時間が経った現在についてなど大幅に加筆。
さらには杉本昌隆八段×藤井聡太二冠の特別編を収録しました。
ぜひ、受け継がれていく「棋士の魂」を感じてください。
※電子版では本文中の写真もカラーで掲載しております。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
94
「絆」という言葉は好きじゃない。そんな陳腐なタイトルが必要ないほど、ここに登場する8組の師弟の物語は胸に熱く迫る。棋士という桁外れの天才同士の師弟を描く野澤さんの文章の、何と熱くて温かいこと。こんな文章が書けるのは、一瞬にして人物の裏の裏まで見抜くカメラマンだからこそなんだろう。ここでは、師弟の美しい部分だけを掬い取っているが、本当は、そんな単純なものではあるまい。でも、それでもいい。怒りや怨みの言葉に溢れたこの世の中だからこそ、愛と感謝に満ちた「師弟」の物語に、心が満たされ、涙が頬を伝う。2021/05/20
さっこ
74
8組の師弟の物語。師弟関係はそれぞれにいろいろな形があるのだけれど、そのどれもが優しく温かく、そして熱い。将棋という厳しい勝負の世界で、棋士たちはとてもストイックだ。辛い奨励会時代、期待に応えられない苦しさや葛藤の中で、確かに繋がっていた師弟関係は、「絆」という言葉では言い表せないほど深いものでした。それぞれの棋士人生に胸が打たれます。豊島竜王が棋聖で初戴冠した時のインタビューで「一番つらかった時期」を聞かれ「25歳から今日まで」と答えたくだりで泣けました。竜王、いつまでも強くいてください。2021/08/02
シャコタンブルー
56
師匠の弟子に対する優しさ、弟子の師匠に対する尊敬の念がヒシヒシ伝わってきた。Abematvの解説等で見かける中田八段。宵越しの銭を持たない「昭和最後の棋士」と呼ばれたエピソードは知らなかった。佐藤天彦九段との最初の出会いからして衝撃だった(笑)。貴族と呼ばれる天彦九段との距離感も付かず離れずでとても素敵な師弟だと思えた。高野五段の新人王のスピーチには感激した、師匠の木村九段が泣くのも当然だ。弟子の過酷な三段リーグでの数々の修羅場、それを祈るように見守る師匠。それは親であり兄のようでもあり輝いていた。2021/04/20
けんとまん1007
55
選ばれし者が、闘う場。切磋琢磨という表現は合わない世界。そんな世界での師弟。それぞれの色合いが、かなり違っていて興味深い。将棋はコマの動かし方を知っているくらいではあるが、ずっと観ている。ここ5,6年、ますます面白くなってきた。テレビなどからはうかがい知れないのが垣間見えて、人と人の世界だなあ~と。もし・・・という言葉は違うかもしれないが、違う師弟の組み合わせだったら・・と考えたりする。しかし、落ち着くべきところに、落ち着くのだろうとも思う。2021/09/21
ポップ
31
棋士の人生は筋書きのないドラマである。師匠と弟子それぞれの将棋との出会い、共に歩んだ道、親子あるいは友人のような関係性に、一般社会にも通じる生き方をみた。木村一基九段と高野智史五段は古き良き師弟だ。高野五段は対局中に正座を崩さず、師匠はずっと強いままでいてほしいと願う。木村九段は「百折不撓」の盤上勝負と弟子の言葉に涙する、飾らない人柄に人気者の素顔が覗いた。高見𣳾地七段は、1年間で栄冠と挫折を経験し成長著しい。20代で小学生を弟子にして結果も出ている。三枚堂達也七段と八代弥七段とは戦友の言葉が相応しい。2021/07/28