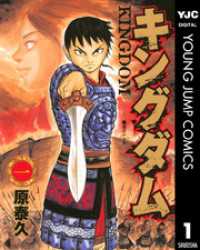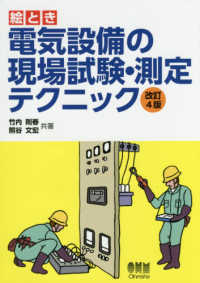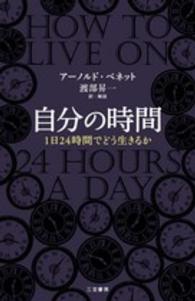内容説明
なにが知的創造を可能にするのか? 批判的読書や「問い」の発見などの方法論を示す。それだけではない。社会のデジタル化が進み、知識が断片化し、大学をはじめ社会全般で知的創造のための社会的条件が弱体化する現在、各人の知的創造を支える図書館や大学、デジタルアーカイブといった社会的基盤はどうあるべきか。AIによる知的労働の代替など、ディストピア状況が到来する可能性が高まるなか、知的創造をいかにして奪還するか――。知的創造の条件を、多角的かつ原理的に論じ切った渾身の書!
目次
はじめに──知的創造の条件とは何か
1 知的創造を語る現代社会
2 対話的行為としての知的創造
3 本書の目的と構成
第1章 はじまりの一歩
1 知的創造は時代と世代に条件づけられている
2 創造的な世代──一八三〇年代生まれと一九三〇年代生まれ
3 第1の出会い──小学校の教室で
4 第2の出会い──キャンパスの芝居小屋で
5 記号のうごめきの中に成立する演劇とは
6 第3の出会い──一九七〇年代の大学で
7 上演論的パースペクティヴ──劇場から盛り場へ
8 第4の出会い──方法としてのカルチュラル・スタディーズ
9 なぜ、実践的な英語力が学びに必要なのか?
第2章 知的バトルのススメ
1 知的創造は、問いの発見から始まる
2 研究を成り立たせる八つの基本要素
3 二つの四角形と二つの三角形
4 方法としての「アタック・ミー!」
5 批判的読書はどうすればいいのか?
6 知のコペルニクス的転換を生む基礎
7 ノリが悪くなって〈問い〉が生まれる
8 〈問い〉はいかに〈研究課題〉に定式化されるか
9 「何のために」「何を」「どのように」の三角形
10 たった一つの概念に研究課題を絞り込む
11 〈問い〉が一つなら、研究テーマは複数のほうがいい?
12 分析枠組は、基軸となる概念の次元からなる
13 異なる分析概念の関係から創造的な仮説が生まれる
第3章 ポスト真実と記録知
集合知
1 ネット社会と知的創造の条件
2 知識における作者性と構造性
3 情報希少の時代から情報過剰の時代へ
4 認知的多様性とフィルターバブル
5 地図を創造する──図書館とグーグル
6 記録知の収蔵庫としての図書館
7 知的運動としてのエンサイクロペディア
8 百学連環・研究会・出版ネットワーク
9 ネット時代の集合知と記録知
第4章 AI社会と知的創造の人間学
1 第五世代コンピュータからAIブームへ
2 言語能力からパターン認識への方針転換
3 シンギュラリティ(技術的特異点)は来るか?
4 「収益加速の法則」という幻想
5 AIは、様々な分野で同じことをしている
6 パターン認識から未来予測へ
7 プロファイリングによる予言の自己成就
8 特異点なきAI社会到来の憂鬱
9 知的労働から掃き出される人間たち
10 AI的思考の彼岸とは何か
11 歴史も社会も非連続に満ちている
12 デジタルアーカイブはAIとどこで異なるのか?
13 デジタルアーカイブはなぜ知的創造の基盤なのか
おわりに──知的創造の歴史的主体とは誰か
1 知的創造をめぐる四つのエージェンシー
2 創造はいつも聴くこと、書くことから始まる
3 他者と未来への信頼を回復する──近代の臨界点にて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
tamami
ほし
かんがく
エジー@中小企業診断士


![ENGLISH JOURNAL BOOK 1[音声DL付]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1449694.jpg)