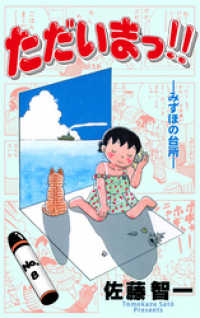内容説明
戦後の日本で歌手、女優として活躍した宮城まり子は、なぜ「ねむの木学園」という家庭をもたず、身体機能に、知恵に障害をもつ子どもたちのための施設と学校をつくったのか――。
「肢体不自由児養護施設」という名称も法律も何もない時代、彼女は、多くの人たちからうけた知恵と勇気に支えられながら、国を動かし、「ねむの木学園」を創設した。
宮城は、「ダメな子なんか一人もいない」といい、教育とは「生きていくお手伝い」という。素朴ともいえるこうした言葉は、彼女のこれまでの“戦仕度の日々”から生まれた厳しくもやさしさに満ちた、子どもたちの幸せを心から願う愛の言葉だった。
「ねむの木学園」は、単に特別支援教育という領域だけに止まらず「教育とは何か」という問いに対して大きな示唆を与えてくれる。人生のすべてを子どもたちに捧げた宮城まり子―-初の本格評伝。
目次
プロローグ
第1部 宮城まり子とねむの木学園のあゆみ
1 宮城まり子の生い立ち
2 学園創設を決意させたこと
3 日本初の「肢体不自由児養護施設」の誕生
4 世界へのアピール──映画制作とテレソン
5 学校法人ねむの木学園ねむの木養護学校の併設
6 さまざまな教育実践
7 肢体不自由児養護施設から肢体不自由児療護施設へ
8 「ねむの木村」の誕生
プロローグ・第1部 出典
第2部 宮城まり子の子ども観・教育観
1 子どもの観方
2 「お手伝い」としての教育
3 「教師」とは何か
4 開かれた学校・ねむの木学園
第2部 出典
エピローグ
1 ねむの木村を散策して0
2 宮城さんと共に──ガーデンハウスにて
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
げんさん
1
「どうせ僕たちは、自転車なんか一生買えやしないや」という言葉に怒りとともに悲しむ。それが原点。2021/08/16
おかぴ
0
障害を抱えている人と会う事が多いが、その変遷について学んだ以上に酷な歴史があったのだろうと思うし、その時代を切り開いて来たという事には脱帽だし尊敬する。理想を謳うだけでは出来ないし、こうやって読んでいる以上の苦労や心労があると思う。僕には出来ない。優しさは強さだとつくづく感じていたがまさにそれの体現と感じる。日本の障害者福祉は遅れていたりと言われているがそれが文化だと言われて納得出来た気がする。後学の為にとても有用な書籍だった。2021/06/29
jouta h.
0
宮城まり子さんがこれほど凄い人と初めて知り自分の無力さを感じざるをえません やさしくね、やさしくね、やさしいことは強いのよ…肝に銘じます2021/05/14