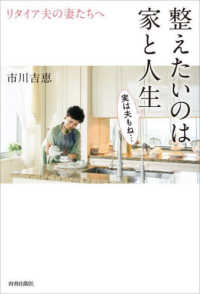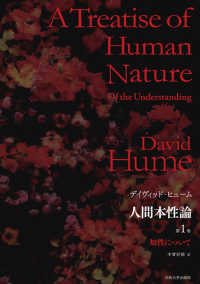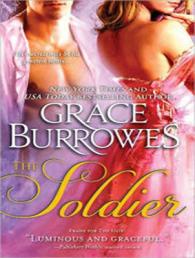内容説明
微生物の生存戦略は、かくもカオスだった! 光合成をやめて寄生虫になった者、細胞から武器を発射する者……。ヘンなやつら、ズルいやつらのオンパレードだ。京大の新進気鋭の研究者が書く、時にずるくしたたかに見える、偶然と驚きに満ちたミクロの世界の生存戦略。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
178
京大式とは?と、初めは思いましたけどね。タイトル通り、変なと言うか、変わった生態の生き物が紹介されましたけど、想定の範囲内と言うかね。 しかし4章も後半に入ると真面目に光合成できる人間についてに考えてみようと。変態考察キターっ!!( ¨̮ )。オチはまぁまぁなんですけど。 取り分け単細胞生物の生態は自由ですなー。共生の関係とか。パーフェクト・ビーストとか、そこからの進化とか。胸熱。 最後の方は、新しい発見についての解説もあり、単細胞生物に性があるとか。マジでか⁉︎2021/07/03
へくとぱすかる
66
単純に動物と植物に分けて、生物の世界をとらえるのは、もう遠い過去のこと。いわゆる系統樹でさえ、細胞内共生という現象を考えると、単純すぎる図式に見えてくる。目に見える生物が増加したエディアカラ紀以後だけを考えては、今の生物のようすを説明できないことがよくわかる。それこそ10億年以上の時間を視野に入れて、化石以前の生物界を考えなければならないようだ。シアノバクテリアが取り込まれて葉緑体になった、といえば簡単に聞こえるが、どれほどの長い年月が必要だったのだろう。微生物こそ生物界の基本(今でも)であるということ。2021/05/25
ホークス
41
2021年刊。生物について勉強になった。旧来の五界説(動物界、植物界、菌界、原生生物界、モネラ界)は不正確で、哺乳類や植物や海藻はそれぞれ別の微生物から進化した。人は体細胞の百〜千倍の微生物を体内・体表に住まわせ、彼ら無しに人体は維持できない。共に進化したからだが、ほんの一瞬の姿でもある。生物間の共生や殺し合いの関係は常に変化していく。進化自体も方向性を持たない。カオスな関係が多様性を創り、変化を乗り越えてきた。恐ろしいマラリア原虫は光合成能力を失った渦鞭毛藻の仲間だとか。頭が揺さぶられて楽しい。2023/01/09
えっくん
31
★★★☆☆図書館から新刊本と紹介され奇妙な生態の生き物の内容と思い予約したのですが、進化の過程で多様な生存戦略を選択した微生物たちを解説した本であり、タイトル名に踊らされた感じも…。もともと真核生物には葉緑体はなく、たまたま細胞内に入り込んだバクテリアが葉緑体となり光合成を始めたという話も興味深いものでした。葉緑体と同様にミトコンドリアも外部からの寄生と考えられていますが、ミトコンドリアが人間を支配する小説「パラサイト・イヴ」を思い出しました。果てしない年月をかけて生物は驚くべき変化を続けているんですね。2021/09/11
to boy
18
微生物の最新情報をわかりやすく記載されているのだが、話があっちこっちに飛んでいろんな情報を食い散らかした感じだし、何が「京大式」なのか分からず、ちょっと期待外れ。でも、原核生物ー真核生物ー多細胞生物と生命が進化してきたという従来の考えが間違っているという話には納得。進化は目的を持っているのではなくたまたまそうなってしまい生き残っているという事だと強調する著者。それにしても藻やら細菌やらの世界の複雑な事に驚き。単細胞生物の多様性と複雑さに感銘しました。2021/04/18
-
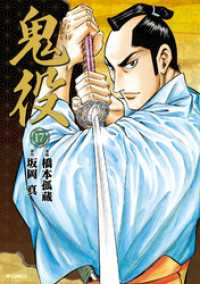
- 電子書籍
- 鬼役 (17) SPコミックス