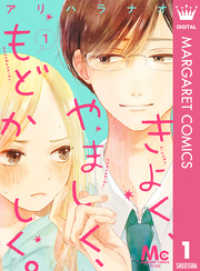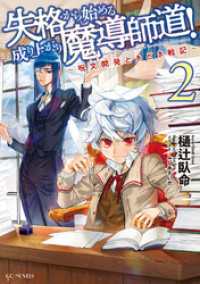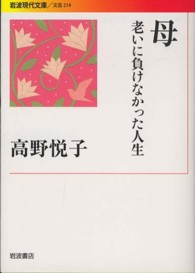内容説明
カモフラージュ、なりすまし、威嚇、死んだふり・・・虫の面白さは「擬態」にあり。なぜ虫はこんな色と形をしているのか。擬態を考察すると人間がわかる。解剖学者・養老孟司の思想の原点。初心者から本格的な虫好き(虫嫌い)まで、圧巻のビジュアルとともに<自然の見方>が学べる1冊。すべての現代人に贈る珠玉の虫エッセイ! オールカラー。
「私が虫なら、ヒトを笑う。こういう生き方があることを教えてやりたいよ」
擬態はゲノムのすることなのに、脳がすることにソックリである。もちろんそれは、神経系の機能の反映だからである。脳はそこに自分の秘密を見る。十九世紀およびそれ以前の科学者たちは、虫がする本能的行動を見て感嘆した。これこそ神の設計にほかならない、と。かれらは進化を知らなかった。だから、本能のほうが先で、神経系がそれに従って形成されたことに気づかなかったのである。かれらは虫を見て、本能を発見したつもりだったが、発見したのは、自分自身の出自だった。いまでもそうは思っていない人は、たくさんいるはずである。脳はなにか特別で、心というはたらきを示す。虫は馬鹿の一つ覚えをくりかえしているだけだ、と。(本文より)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
86
生物の情報系は遺伝子系と神経系の2種類あり、生物は合目的的な行動をとる。虫は遺伝子系を介して本能的に行動する。ヒトは脳を介して意識的に行い、可塑性が大きいため自分の行動を自分で決めたと思い込む。脳がゲノムを真似て行動するよりはるか昔から、数十億年をかけて合目的的行動をゲノムに組み込んできたのが虫である。擬態とは長い進化の過程から生み出されたもので、それを学ぶのはヒトであり、教えてくれるのは自然なのである。マルクス・ガブリエルの「国家規模の擬態が起きている」とは社会の情報化が進んだ姿ということに他ならない。2021/05/04
shimashimaon
7
ヤマザキマリさんとの対談本を読んで、昆虫に興味が湧き、図鑑を探していて本書と出会いました。綺麗な、不思議な昆虫の写真をたくさん鑑賞できます。美しいメタリック色、気味の悪い警戒色、不思議な形etc.。枯葉の擬態など良く知られたものの他に、雌雄の形態の違いやどこにでもいる虫までもテーマにしていて面白いです。私は嫌いだった蛾(ヤマザキマリさんとの対談本にもマニアが登場する)にとりわけ惹かれています。脳のアナロジー機能、遺伝子系と神経系という二つの情報系の関係など大いに学びながら、多様な世界を眺めていきたいです。2023/02/04
ジャスミン
6
お見事に尽きる。 擬態の奥深さ。真似ること、大切にします。 養老さんの文章はとても楽しいです。 最後に出てきた、ホタルに似たゴキブリ うーん、考えさせられた2022/07/19
yooou
6
☆☆☆☆★ 養老先生初挑戦でした。とても面白い本でした。昆虫は本能によって自動的に行動していて意識とよべるものはないというのが基本スタンスなんですね。僕は人間とは異なるレベルではあるけれど意識と呼べるものがあると思うのだけど本当のところはどうなのでしょうね2022/03/18
隠者
2
写真がたくさん載ってて虫の凄さがよくわかる本。ただ、あくまで触りという感じで写真と軽い説明で「ね、凄いでしょ?」という感じで虫好きが虫の凄さを一生懸命説明してるというような。知識も何もない人間なので「うん、凄い!」で完結してしまうのは惜しいというか興味があったら別の本読みなさいと誘導されているというか。とにもかくにも虫の生体を写真を見るだけでこれだけ伝わるのだから本気で研究のし甲斐はあるのだろうと思う。こういうの見ると新種と個体差かなんて区別の付けようがないから新種が見つかるのもさもありなん。2022/01/14